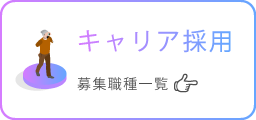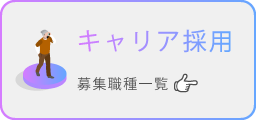アートとコードの融合。
Vol.2 デジタルアートの世界
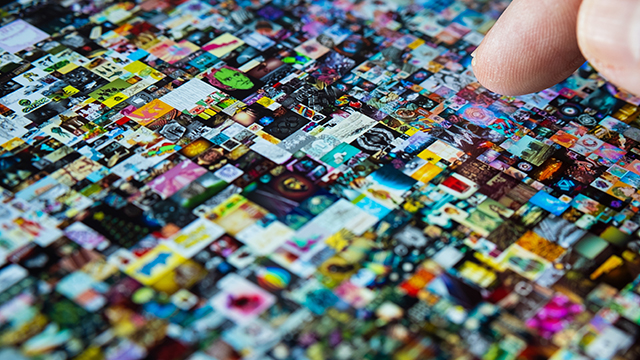
近年、プロジェクションマッピングの普及や、大規模なデジタルインスタレーションの成功で、多くの人に広く知られるようになったデジタルアートの世界。
「アートとコードの融合」をテーマに前後編2回にわけて紹介しています。今回は後編「デジタルアートの歴史と、近年注目を浴びたデジタルアートの実例」を紹介していきます。
前編の「デジタルアートの概要とクリエイティブコーディング」についてはこちらから。
テクノロジーとアートの歴史
まずは、テクノロジーとアートの歴史から振り返っていきましょう。
1950年代:デジタルアートの夜明け
「コンピューターアート」としての最初の作品は、1952年にアメリカの数学者・芸術家であるベン・F・ラポスキーが、ブラウン管とアナログコンピューターを駆使して制作した「Oscillon No.4」とされています。
1960-70年代:結びつくアーティストとエンジニア
そして、早くも1966年には、アーティストとエンジニアを結びつける試みである、パフォーマンスアート・プレゼンテーション「9 Evenings: Theatre and Engineering」が開催されています。
これを主催した、前衛芸術家たちの集い「E.A.T.(Experiments in Art and Technology)」は、1970年の大阪万博において、現代の没入型デジタルアートの先祖にあたる「ペプシ館」をプロデュースしています。これは、多くの日本人がデジタルインスタレーションアートに触れたもっとも古い体験のひとつです。
1980-90年代:VRの登場
メディア・アート界のパイオニアであるジェフリー・ショーが1989年に発表した「The Legible City」は、固定された自転車を漕ぐことで、3DCGの仮想都市を駆け抜けることができるデジタルアート作品です。これは、「VRシステム」を使用したごく初期の作品として知られています。
1997年には、イリノイ大学において開発されたVRシステム「CAVE」が登場。これは、3Dメガネをかけることで立体映像が広がる仕組みで、中央に設置された人形を操作すると仮想世界のパラメーターが変化する試みがなされていました。
日本におけるデジタルアート
日本にも有名なデジタルアーティストがいます。たとえば、ウゴウゴルーガなどで名前を知られた岩井俊雄氏が、坂本龍一氏とのコラボレーションによって1995年に発表した「映像装置としてのピアノ」は、日本における初期デジタルアート/メディア・アートを代表する作品といえます。
近年では、Perfumeのライブのテクノロジー及びディレクションを努める、エンジニア集団「ライゾマティクス」の真鍋大度氏が有名です。フェンシングを視覚的に見せる「フェンシング・ビジュアライズド」の技術開発や、リオ五輪の閉会式の映像ディレクションを担当するなど、世界的にも高い評価を受けています。
そして今、日本のみならず海外からも注目されているのが、プログラマー・エンジニア・建築家・アニメーターなどからなる「チームラボ」です。大規模な施設を必要とする体験型デジタルインスタレーション作品でありながら、今までない規模での常設展示を実現し、日本におけるデジタルインスタレーションアートの知名度を押し上げました。
プログラムが生成するアートに魅せられるエンジニアたち
コンピュータープログラムによって生成・構築されるデジタルアートのことを、一般に「ジェネレーティブアート」と呼びます。
これは、デジタルツールによって描かれた絵画やデジタル写真を用いたコラージュ作品、2D/3Dコンピューターグラフィックスのように、人間が思い描くアートを描画する手段としてコンピューターを使う方法とは異なり、自律的に動作する機構(つまりプログラム)を作り、それがアート作品を作り出します。
人間が行うのは、ペンタブレットのペンを握ることではなく、プログラムの作成です。そしてこのプログラミングは自然科学的なアルゴリズムを主体とするものが多く、複雑性の度合いは時間と共に増していき、作り手にとっても予測のできない挙動を見せ、時に予測を超える結果をもたらします。
このようなデジタルアート作品に触れ、デジタルアートの魅力や可能性を感じた理系分野を得意とするエンジニアたちが、デジタルアート分野に参入するケースが増えています。製作者には優れた数学的な能力と、高い実装技術が要求されますが、そうした事実も優秀なエンジニアにとっては魅力的な挑戦なのです。
デジタルアート3つの事例
続いて、デジタルアートの事例をご紹介します。リアルタイムの体験型、屋外大規模空間でのAR(拡張現実)、そして、触れてカタチを変えられる光、の3作品です。
お絵かき水族館(teamLab)
「teamLab(チームラボ)」2013年にスタートした「お絵かき水族館」は、子供が描いた魚の絵をその場でスキャンし、そのスキャンした絵の魚がスクリーンに映し出された海の中をすぐに泳ぎ回るという、リアルタイムかつ参加型のアートプロジェクトです。
魚たちがただ泳ぎ回るだけでなく、泳いでいる魚の映像に触れると、いっせいに逃げ出したり、反対に、エサ袋に触れてエサをあげることもできます。
この作品は、教育的プロジェクト「学ぶ!未来の遊園地」として、日本だけでなく、台湾、タイ、アメリカでも開催されました。イタリアやドバイでは常設展示され、世界中の「お絵かき水族館」をリアルタイムで繋いだ「世界とつながったお絵かき水族館」 も登場するなど、年々進化を続けています。
リオオリンピック閉会セレモニー(真鍋大度氏ほか)
2016年リオオリンピック閉会式で、世界的に話題になった、現実空間にはないものを現実空間上に合成するAR(拡張現実)テクノロジーによる演出です。
このシーンを担当したのは、Perfumeのライブの演出などで知られる、ライゾマティクスの真鍋大度氏。東京オリンピックで行われる競技種目の選手の姿を模した映像が、土砂降りの会場の上空に、美しく映し出されました。
これらの演出は、レーザースキャナーでスキャンしたスタジアムの形状と、リアルタイムでセンシングした映像を融合させて、仮想空間を実現させる手法で成り立っています。
Fairy Lights in Femtoseconds(落合陽一氏 )
「触れることのできる光」のアートです。空中に浮かぶ、光で描かれた象(3D映像)に触れると、その光の象がカタチを変え、触れたことが指でもわかります。
注目すべきは、レーザーで精緻な三次元像を描くだけでなく、触れた感触を得られることです。これにはフェムト秒レーザーという技術を使っており、これはナノ秒レーザーなど他の方式よりも安全性が高いことも検証されています。
この作品では、大掛かりな設備を使い1cm四方程度の投影を実現しています。今後の研究によって、より大きなサイズの投影が可能になれば、空間立体ディスプレイの実用化も見えてくる興味深い作品といえます。
まとめ
「アートとコードの融合」をテーマに、前後編の2回に渡りデジタルアートについて解説をしてきました。
デジタルアートとはなにか、どのような技術(プログラミング言語)で作られ、どのような作品が生まれているのか、前後編を通してお楽しみいただければと思います。
「アート」と言っても、それが指す意味の幅は広く、意味にも確実にゆらぎがあります。そしてそのゆらぎや、カテゴライズが難しい特性そのものがアートの魅力であり、別分野のエンジニアを引きつける魅力にもなっていると言えるでしょう。