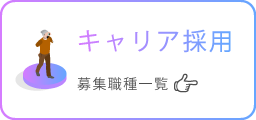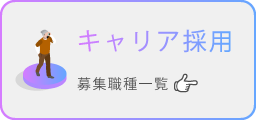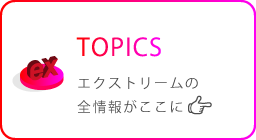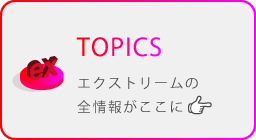DX補助金情報Vol.3
中小企業のDX化事例17選【補助金活用】
DX補助金をわかりやすく解説する本連載。第3回では中小企業のDX化事例として「IT導入補助金」「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」の3種を対象に、実際に制度を活用して成果を上げた事例を業種別に紹介します。
業務効率化や新規事業の立ち上げ、生産性向上など、多様な目的でDX補助金が活用されている実態を把握できる内容です。
自社のDX推進を検討している経営者さまや担当者さまは、具体的な活用イメージや制度選定の参考にぜひお役立てください。
【IT導入補助金】7つの活用事例

IT導入補助金は、業務の効率化や生産性の向上を目的に、ITツールを導入する際の費用を支援する制度です。多くの中小企業がこの制度を活用し、会計や受発注管理、顧客対応、情報共有など、業務のデジタル化を実現しています。
補助対象のITツールは事前に審査・登録されたものに限られ、「IT導入支援事業者」との連携が申請要件です。
実際に補助金を活用して課題を解決し、成果を上げた7つの事例をご紹介します。
・製造業:構造計算への対応強化に向けCADソフトを導入
・卸売業:リアルタイム経営を実現する会計ソフト導入
・不動産業:クラウド会計ソフト導入で組織改革と意識醸成を実現
・広告業:オンライン英会話事業を補助金で新規立ち上げ
・飲食業:セルフオーダー導入で人手不足解消と売上40%増
・福祉業:介護ソフトの刷新で業務負担を軽減
・専門・技術サービス業:制度改正に備え整備業務をデジタル化
業種ごとの課題と導入効果を具体的に解説するため、ぜひ取り組みの参考にしてください。
製造業:構造計算への対応強化に向けCADソフトを導入
木質部材の製造販売を行う企業では、建築基準法の改正を契機に構造計算業務を自社対応できる体制を整えるため、IT導入補助金を活用しCADソフトを導入。新たに専門部署も設置し、技術者の育成が順調に進んでいます。営業面の成果は今後に期待されるものの、社員のモチベーションが高まり、事業拡大への足掛かりとして大きな成果をあげています。
卸売業:リアルタイム経営を実現する会計ソフト導入
国産時計などを取り扱う卸売企業では、基幹システムの更新にあわせて、IT導入補助金を活用し会計ソフトを導入。リアルタイムで経営数値を把握できるようになり、粗利目標や事業戦略を社内で共有しやすくなりました。導入前は税理士任せだった数値管理が可視化され、意思決定のスピード向上と社員間の意識改革につながっています。
不動産業:クラウド会計ソフト導入で組織改革と意識醸成を実現
アパート・マンションの管理や不動産再生を手掛ける企業が、IT導入補助金を活用してクラウド型会計ソフトを導入。属人的に管理されていた情報を集約し、データの一元化を推進しました。導入を機に社員の意識も変化し、会議や制度見直しを通じて、会社全体でデジタル化を受け入れる体制が整備されつつあります。
広告業:オンライン英会話事業を補助金で新規立ち上げ
ホームページ制作を主業とする広告会社が、コロナ禍での業界変化に対応し、新たな収益源を確保するためにIT導入補助金を活用。オンライン英会話サービスを新規事業として立ち上げました。オフライン中心の業務から脱却し、時代に合った事業モデルに挑戦。導入後には課題も見えたものの、新たな方向性の確立に向けた大きな一歩となりました。
飲食業:セルフオーダー導入で人手不足解消と売上40%増
カフェを運営する企業が、慢性的な人手不足と回転率の改善を目的に、IT導入補助金を活用してセルフオーダーシステムを導入しました。注文から支払いまでを自動化することで業務負担が軽減され、従業員の定着率も向上。結果として売上は約40%伸び、新商品の開発にもリソースを回せるようになるなど、多方面で効果が表れています。
福祉業:介護ソフトの刷新で業務負担を軽減
特別養護老人ホームを運営する法人が、古くなった介護記録ソフトを刷新するため、IT導入補助金を活用。タブレット対応のクラウド型ソフトを導入したことで、現場での入力作業がスムーズになり、1人あたり10~20分の作業時間削減を実現しました。高齢者介護の現場における業務効率化と、従業員の働きやすさの向上につながっています。
専門・技術サービス業:制度改正に備え整備業務をデジタル化
自動車整備業を営む企業が、業界の制度改正への対応と業務効率化を目的に、IT導入補助金を活用して整備システムを導入。検査・車検・顧客情報の管理を一元化できる仕組みにより、監査対応の簡素化やヒューマンエラーの削減を実現しました。従業員のITリテラシーも向上し、変化に強い職場環境づくりが進んでいます。
【事業再構築補助金】5つの活用事例
事業再構築補助金は、ポストコロナの環境変化に対応し、業態転換や新分野進出、事業再編など思い切った挑戦を支援する制度です。
新たな設備投資やビジネスモデルの構築に活用されており、多くの中小企業がこの制度を活かして事業を再構築しています。
申請には「認定経営革新等支援機関」から事業計画書の確認を受けることが必須要件となっており、計画性と実行力が問われます。変革を目指す企業にとって非常に有効な支援制度です。
本記事では、実際に採択された案件である、次の5つの事例をご紹介します。
・宿泊・飲食サービス業:インバウンド対応へテイクアウト型カフェに業態転換
・建設業:農業の課題解決に向けた自動野菜栽培システム事業を展開
・建設業:高精度内装材の製造と取付体制を一貫構築
・製造業:医療機器の安定供給に向けた生産拠点を新設
・情報通信業:住宅購入者と工務店をつなぐマッチングサービスを構築
どのような事業内容に事業再構築補助金が活用されたのか、くわしく見ていきましょう。
宿泊・飲食サービス業:インバウンド対応へテイクアウト型カフェに業態転換
観光客向けの日本茶カフェを新たに立ち上げた飲食企業が、事業再構築補助金を活用。イートイン中心だった店舗形態を、テイクアウト・デリバリーに強い業態へとシフトしました。コロナ禍で定着した「持ち帰り文化」に対応しつつ、インバウンド需要の回復を見越した事業モデルにより、売上回復と感染対策の両立を実現しています。
建設業:農業の課題解決に向けた自動野菜栽培システム事業を展開
建設業と農業に精通する企業が、事業再構築補助金を活用し、自動野菜栽培システムの建設・販売事業を新たに展開。既存の顧客基盤と施工ノウハウを生かし、就業人口が減少する農業分野において、生産性向上と持続可能性の確保に貢献する仕組みを導入しました。事業の多角化とともに、新市場への参入を図っています。
建設業:高精度内装材の製造と取付体制を一貫構築
国内の工場建設需要の高まりを背景に、建設会社が事業再構築補助金を活用し、高精度内装材の製造と現地取付までを一括対応する新事業を立ち上げました。製材から施工までの一貫体制を構築することで、工期短縮や品質管理の向上を実現。半導体工場など大規模案件への対応力を強化し、受注拡大を目指しています。
製造業:医療機器の安定供給に向けた生産拠点を新設
地域の医療機器メーカーからの増産要請に対応するため、製造企業が事業再構築補助金を活用し、新たな生産拠点を整備。先進設備の導入によって生産能力を約20%向上させ、安定供給体制を強化しました。これにより、地域内の医療機器供給体制が整い、企業としての信頼性と対応力を高める結果につながっています。
情報通信業:住宅購入者と工務店をつなぐマッチングサービスを構築
情報通信系企業が事業再構築補助金を活用し、新築戸建て購入者と地域工務店をつなぐWebマッチングプラットフォームを構築。利用者はWeb上で外装・内装のカスタマイズが可能となり、理想の住まいをイメージしやすくなりました。省力化と集客支援を同時に実現する仕組みとして、工務店の業務効率化と受注拡大を後押ししています。
【ものづくり補助金】5つの活用事例
ものづくり補助金は、中小企業の生産性向上や新製品・サービスの開発、業務プロセス改善を支援する制度です。先進設備の導入やIT化によって、競争力の強化や働き方改革につなげる取り組みが進んでいます。
働き方改革やインボイス対応といった制度変更への備えとしても活用されており、長期的な成長を目指す企業に向けた補助金です。
ここでは、実際に補助金を活用して成果を上げた5つの事例をご紹介します。
・製造業:CFRP技術を活かした歩行アシスト装具の開発とブランド展開
・飲食・宿泊業:魚介類の鮮度を活かしたデリバリー・テイクアウト事業を強化
・製造業:全工程内製化とIT活用で高級包丁の量産体制を確立
・製造業:IoT導入と人材育成で高精度金型の生産性を向上
・農業:紫蘇の加工・販売で収益性と雇用の多様性を実現
製造業から農業分野まで、幅広い業種での活用例をもとに、どのような変化が生まれたのかを見ていきましょう。
製造業:CFRP技術を活かした歩行アシスト装具の開発とブランド展開
高機能素材CFRP(炭素繊維強化プラスチック)の加工技術を持つ製造企業が、ものづくり補助金を活用し、脊髄損傷者向け二足歩行アシスト装具を開発。無動力で膝関節の動きを実現する独自構造を採用し、国内外での展開に向けたブランドを立ち上げました。国際特許出願も進め、医療・福祉分野への参入を加速させています。
飲食・宿泊業:魚介類の鮮度を活かしたデリバリー・テイクアウト事業を強化
宿泊施設を運営する企業が、コロナ禍による売上減少に対応するため、ものづくり補助金を活用。魚介類を使ったテイクアウト・デリバリー事業を強化するために、専用ホームページを開設し、真空包装機や特殊冷蔵庫を導入しました。品質保持と作業効率を両立し、ITを活用した商品管理やSNS発信で新たな顧客層の開拓にも取り組んでいます。
製造業:全工程内製化とIT活用で高級包丁の量産体制を確立
刃物の産地・関市で創業した老舗企業が、ものづくり補助金を活用し、高級包丁の全工程内製化とIoTを活用した生産体制を構築。伝統技術と最先端設備を融合させ、世界市場を視野に入れた品質管理と量産体制を実現しました。海外富裕層向けOEM商品や自社ブランドの展開を通じて、地域の産業価値向上にもつながっています。
製造業:IoT導入と人材育成で高精度金型の生産性を向上
高精度な金型製造を行う企業が、ものづくり補助金を活用してIoT環境と高性能加工機を導入。設備ごとの稼働状況を可視化し、柔軟な生産計画が可能となりました。加えて、多能工化を促す人材育成と評価制度も整備。技術継承と効率化を同時に実現し、短納期・低コストでの対応力を高めています。
農業:紫蘇の加工・販売で収益性と雇用の多様性を実現
紫蘇の生産から加工・販売・輸出までを一貫して行う農業法人が、ものづくり補助金を活用。ICTや自動選別機の導入により作業効率を飛躍的に向上させ、品質管理と出荷体制を強化しました。紫蘇オイルや粉末などの加工品も開発し、ブランド化と販路拡大を推進。女性や高齢者、外国人材も活躍できる現場づくりを進めています。
DX補助金の申請~採択後までの流れ
DX補助金は、申請から受給までに複数のステップがあり、計画的な対応が欠かせません。
詳細な手続きは制度により異なるため、最新情報を確認しながら進めましょう。詳しくは別記事「DX補助金申請マニュアル|申請から採択後までの全ステップ」で解説しています。
DX補助金の注意ポイント
DX補助金を活用するには、申請時の注意点を把握しておくことが重要です。制度ごとに条件や手続きが異なるため、要件を満たしていないと申請が無効になることもあります。
ここでは、特に見落としがちな次の3つのポイントを解説します。
・申請期間がある
・審査がある
・自己資金が必要になる
DX補助金の注意ポイントを正しく理解し、確実な申請・活用につなげましょう。
申請期間がある
補助金には必ず申請期間が設けられており、期間内に手続きを完了する必要があります。1か月以上の募集期間があるケースもあれば、数日間しかない短期間の公募もあるため、はじめに確認するのがおすすめです。
申請直前に必要書類が揃わず間に合わなかった、という例も少なくありません。希望する制度が見つかったら、できるだけ早めに準備を始めることが重要です。
審査がある
補助金は申請すれば必ず支給されるわけではなく、所定の審査を通過する必要があります。書類に不備がある場合や、募集要項に合っていない内容では採択されません。
また、予算の上限があるため、募集期間中でも早期に締切られる可能性があります。計画性と正確な書類作成が求められることを理解しておきましょう。
自己資金が必要になる
補助金は事業完了後に支給される「後払い」が基本です。また、支給額は費用の1/2や2/3などにとどまるため、全額を補助金でまかなうことはできません。
そのため、事業開始時点で必要な資金を確保しておくことが不可欠です。資金が不足している場合は、金融機関からの融資を含めた資金計画を立てる必要があります。
DX補助金の活用事例から学ぶ、中小企業のデジタル化成功のポイント
DX補助金の活用は、中小企業がデジタル化を進めるうえで極めて有効な手段です。
IT導入補助金、事業再構築補助金、ものづくり補助金といった制度を活用することで、業務効率化・売上向上・新規事業の立ち上げなど、さまざまな成果を実現した事例が多数あります。
本記事で紹介したDX補助金の事例を参考に、自社の目的や課題に合った補助金制度を見極めることが、成功への第一歩です。申請の流れや注意点も押さえながら、持続可能な成長に向けたDX戦略を検討してみてください。