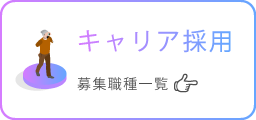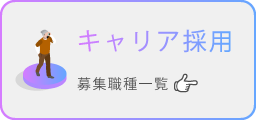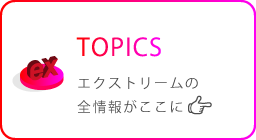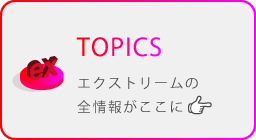「関西学生eスポーツコミュニティのハブに」
近畿大学に設備「esports Arena」の狙いや大学eスポーツの意義を聞く
近年はeスポーツ用途で利用できる高性能なPCを備えた施設が各地で見られるようになっています。中でも特殊な存在と言えるのが大阪の私立大学である近畿大学が2022年に開設した「esports Arena」です。

31台のゲーミングPCに加え、配信用設備とオペレーション席を完備。実況解説のための音響も整い、60人収容の観客席まで用意された施設は、教育機関どころか一般利用が可能なeスポーツ施設としても珍しいほどの規模です。
なぜ近畿大学にはこれほど大規模で本格的なeスポーツ施設が作られたのか。その狙いや意義、そして大学におけるeスポーツの位置づけを、近畿大学情報学部学生センターの矢藤邦治氏にインタビューでお聞きします。
──最初に自己紹介をお願いします。
矢藤 1991年に近畿大学に入職して、20年近く学内のシステム導入やネットワーク設計など情報システム部門を担当しておりました。現在は情報学部学生センターという主に教務関係や入試など学部に関する運営事項を扱う部署で事務長を務めています。
eスポーツとの関わりでは、esports Arenaは近畿大学情報学研究所の施設という位置づけになりますが、私は研究所事務の兼務として施設の管理運営やイベントのプロデュースも行っています。
私個人としても昔からPCやコンシューマ機に関わらずゲームがずっと好きで、現在は近畿大学eスポーツサークルの顧問も担当しています。
──まずは2022年に開設されたesports Arenaについてお聞きします。施設の設置に至ったのはどのような経緯だったのでしょうか。
矢藤 近畿大学では3年前に理工学部情報学科を情報学部へと昇格させました。この学部開設にあたり学生募集のためのブランドイメージの構築を進めました。そのPRの一環としてeスポーツを採用させていただいた、というのが大きな背景になります。
2030年にはIT人材・エンジニアの数が大きく不足するという予測も発表されていますが、この状況を受けて近畿大学は高等教育機関として「エンジニア育成を担う学部が必要だろう」と学部昇格の構想をスタートさせていました。申請などの手続きもあり学部開設は2022年となりましたが、初期構想はその5年ほど前だったと思います。
──eスポーツ以外ではどのような要素がブランドイメージ構築に採用されたのでしょうか。
矢藤 情報学部の学部長はプレイステーションの開発者として知られる久夛良木健氏で、特別講義も開催されています。また、情報学部の教員がトレーナーの資格を取得し、Apple社の認定するプログラマー資格を取得できる専用の施設「AATCE」を設置しています。esports Arenaの開設も含めまして「プレイステーション」「Apple」「eスポーツ」というZ世代にも馴染みのあるフレーズからブランドイメージを構築しています。
情報学部は授業の約半分がオンラインで受講できるという特徴もありますが、そうしたカリキュラムの中にはイベントの運営企画に関する授業もあり、教育に積極的にeスポーツを取り入れています。
──先進的な取り組みの多い学部だと感じますが、「AATCE」もesports Arenaも非常に設備内容がハイレベルだと感じます。これだけの施設を設置するのは大変だったのではないでしょうか。
矢藤 構想段階では「高校生が情報やITと聞いてイメージすることは何か」をテーマに、普段から情報端末としてスマートフォンに触れている高校生なら誰でも知っている「Apple」や、人気のある「eスポーツ」が学部イメージを上手く伝えるキーワードになるのではと考えました。採用に至るまでには根拠となる数字を資料として上層部へのプレゼンなども必要となったのですが、学部の宣伝費と考えれば問題無いということで承認を得て、これだけの設備を用意することが出来ました。
──私立大学としてブランドイメージの構築には最終的に入学希望者を増やすという目的が大きいかと思います。実際の効果や利用状況はいかがでしょうか。
矢藤 2023年のデータでは1年間のesports Arenaの延べ利用者数は約9,700人で、長期休暇を除いた9カ月の稼働であることを考えると平均して月の利用者数は延べ約1,000人ですね。利用率はお昼頃を中心に高く、繰り返しの利用者も増えてきて満席になっていることも多いです。
利用者へのアンケートでは約40%が入学前からesports Arenaの存在を知っていたとの回答がありました。もちろんこれだけでは「eスポーツ施設があるから入学した」とまでは言えませんが、少なくとも進学先を選ぶ要因のひとつにはなっているのではないでしょうか。
──施設のことを知ってから中高生の進路決定に反映されるまでの時間を考えると、今年度以降も「esports Arenaがあるから」という受験生が増える可能性は少なくないのではないでしょうか。
矢藤 学部昇格に際して定員を190名から330名へ約180%増やしたのですが、初年度の志願者数は前年比250%増とかなりの伸び幅になりました。2022年は他の大学でも情報系の学部が増えつつあるタイミングで、ブランドイメージ戦略がなければここまで増えることはなかったと思われます。
ただ、その結果として志願倍率がかなり高くなってしまったので2年目(2023年度)は受け控えの傾向が見られて受験者数は少し下がっています。今後も同様の動きは考えられますので、動向には注目しています。
──eスポーツに関心が高くても倍率の高さがハードルになってしまう可能性もあるのですね。
矢藤 定員割れになっている大学もありますから贅沢な悩みではありますが、せっかくの高偏差値を維持していきしたい気持ちはありますね。eスポーツが学生募集に効果を発揮していることは数字を見て実感しています。
──実際の利用者の傾向や反響はいかがでしょうか。
矢藤 アンケートによれば利用動機は「高性能なPCがあるから」と「空き時間だったから」が大多数を占めています。タイトルでは『VALORANT』が圧倒的な人気で、8割くらいの方にプレイされていると思います。

──大学の空きコマに高性能PCでeスポーツタイトルをプレイするという過ごし方は非常に羨ましいですね。大学内のeスポーツサークルの顧問も務められているということで、そちらについてもお聞きします。在籍人数はどのくらいになるのでしょうか。
矢藤 いわゆる幽霊部員も含めますと300人近いかと思いますが、積極的に稼働しているメンバーは50人程度かと思います。タイトルごとで部門を分けて活動していまして、やはり人気は『VALORANT』ですね。それ以外にも『Apex Legends』や『ストリートファイター』などで活動しているプレイヤーもいます。
──学生eスポーツはなかなか成果発表の場といえるような大会がまだまだ少ないのが現状かと思いますが、近畿大学eスポーツサークルはどのような活動を行っているのでしょうか。
矢藤 高校生くらいまでの若者にとってeスポーツとは「家庭でゲームをしている延長線上」のような感覚だと思いますが、我々にはイベントや配信ができるesports Arenaという環境が整っていて、実況席もあります。これによってイベントの企画・運営や配信を通じて「eスポーツを興行性の高いエンターテイメントとして実践」することが可能になっているのが大きいと考えています。

サークル内にはイベント企画運営を専門とする「クリエイターズ部門」があり、年5回のオープンキャンパスで実際にイベント運営をしています。そうした機会もあって、本学の学生は「単にゲームをやっているだけ」ではなくエンターテイメントとしてeスポーツを捉え、ビジネスとしての視点を持ちながらキャリア形成につなげられていると思いますし、これこそが大学がeスポーツをやっている一番の意義ではないかと思っています。
──eスポーツの現場に限らず、社会で活躍できる能力が磨かれているのですね。
矢藤 経済産業省が打ち出している「社会人基礎力」という能力があるのですが、これは「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」という3要素で構成されています。これらはなかなか授業で学ぶ機会は得られませんから、eスポーツのイベント企画や運営を通じて学べるのは貴重な機会だと思います。もちろん企画運営だけでなく自分でプレイをする場合にも戦術を考える力であったり、チームプレーに取り組む姿勢は教育に貢献するものがあり、eスポーツから学べることは多いと考えています。
──なかなか近畿大学さんほどの施設を持てるケースばかりではないと思いますが、大学eスポーツ全体がもっと活発になると更なる相乗効果も望めるのではないでしょうか。
矢藤 他の大学さんでも少しずつ施設やイベントを導入するケースも聞かれるようになっていますので、私どもとしても大会の誘致や学生大会の開催を通じて高校生にもどんどんPRをしていかなければなりませんし、現在はそこに取り組んでいる段階です。
──今後の取り組みでチャレンジしたい内容などはありますか?
矢藤 中学校はまだ多くないと思いますが、高校では部活動としてeスポーツを「はじめよう」という段階の学校さんが少しずつ増えているように思います。大学に比べると自前の施設は持ちづらく十分な環境を用意できないという実情があるようですから、そうした現場に対してeスポーツで支援出来ることはないかなと最近は考えています。
そのために部活動で顧問をされている先生を訪問してコミュニティを作っていきたいと思っていますし、大学の近隣校でしたらアリーナを貸し出してイベントなどでご利用いただくことも可能です。もちろんビジネスとしてeスポーツ施設を持たれている企業様の邪魔にはならないよう学校さん相手に限定してですが、無償での貸し出しを検討しています。
あとはサークルの学生を部活動のコーチのお手伝いとしてボランティア派遣していくことも考えられます。そうした活動から中学・高校のeスポーツコミュニティをもっと作っていけなければいけないという使命感もあり、その背景に「将来的に近畿大学を受験してくれたら」という想いもありますが、私たちでやれることは探っていきたいですね。若年層におけるeスポーツコミュニティのハブ的役割になれたらというのが適切な表現かもしれません。
──学生のeスポーツコミュニティが盛り上がれば、関西のeスポーツもさらに盛り上がっていくことも予想されます。
矢藤 近畿大学としては大阪府におけるeスポーツを活用した取組みを促進するため11月14日に発足した「大阪eスポーツラウンドテーブル」にも参加しており、大阪らしい発展にも取り組んでいきたいと考えています。eスポーツ関連のイベントにはどんどん顔を出していきたいと思っていますので、見かけたらぜひ声をかけていただきたいですね。
──今後のeスポーツへの取り組み方、向き合い方にも注目しています。本日はありがとうございました。
矢藤 ありがとうございました。