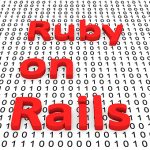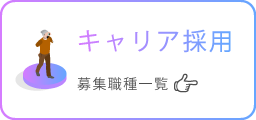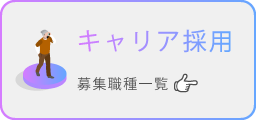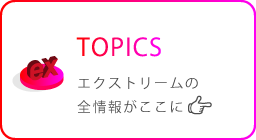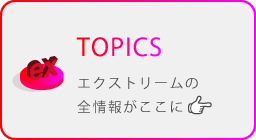量子コンピュータの現在地 仕組みや最新動向をわかりやすく解説します
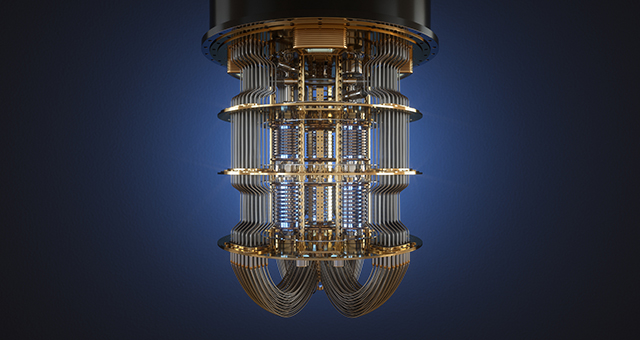
研究・開発が進められている量子コンピュータは、高速演算を実現する新しい技術です。しかし、その仕組みや現在の実力、そして解決すべき課題など、量子コンピュータをめぐる状況がよくわからない方は多いのではないでしょうか。
ここでは、量子コンピュータの基礎や現状、最新動向から課題まで、わかりやすく解説します。
量子コンピュータとは?
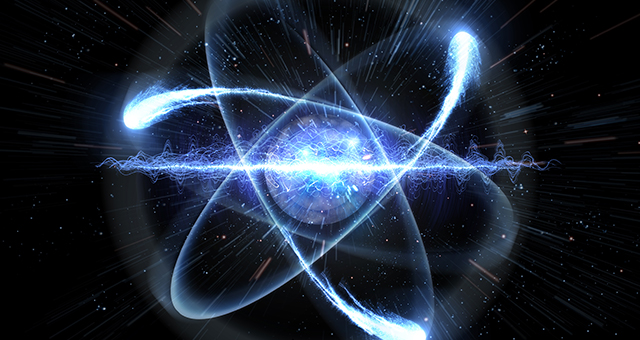
まずは「量子コンピュータ」がどのようなものかについて、仕組みや種類、得意分野などを解説します。
そもそも「量子」とは何か
量子(りょうし)とは、目に見えないほど小さな物質やエネルギーの単位のこと。例えば量子には次のようなものがあります。
【代表的な量子の一例】
・原子
・原子を形づくる電子
・中性子
・ニュートリノなどの素粒子
原子や中性子、ニュートリノといったことばをニュースなどで聞いたことがあるのではないでしょうか。これらはすべて量子の一部です。
量子の大きさは、ナノサイズ(1mの10億分の1)以下。これほど小さくなると、私たちが知っているニュートン力学(慣性の法則、運動方程式、作用反作用の法則)などの物理法則が通用しません。量子は粒子の性質と、波動の性質をあわせ持ち、「量子力学」という不思議な法則が作用しています。
量子コンピュータの仕組み
量子に作用する「量子力学」は、私たちの知っている物理法則とは異なり、直感で理解できない不思議な現象が起こります。量子コンピュータとは、量子が起こす不思議な特性を利用して計算・情報処理を行うコンピュータです。
量子コンピュータに用いられる、代表的な量子力学に「重ね合わせ」があります。従来のコンピュータはビットを「0」と「1」のどちらかの状態で表現していました。しかし、量子コンピュータでは「重ね合わせ」の原理を利用することで、「0」でもあり「1」でもある状態をつくり出せます。
従来1つのビットで「0」か「1」を表現していたところ、量子コンピュータでは「0」と「1」の情報を同時に表現できるため、並列計算を超高速で行えます。
もう1つが「量子もつれ」です。量子同士は相互作用すると非常に強い相関を示す特性があり、例えば、一方の量子が1なら、もう一方の量子も1となります。この「量子もつれ」の原理を利用すると、相互作用している複数の量子を効率よく操作できるようになります。
こうした、従来の学問では説明できない、いわば「量子のふるまい」こそが、量子コンピュータが注目されている理由の1つです。
出典:2022年ノーベル物理学賞「量子もつれ」とは|産業技術総合研究所
実用化を目指す2つの量子コンピュータ
量子コンピュータには、「量子ゲート方式」と「量子アニーリング方式」という2つの方式があります。
汎用的な計算に向いているのは前者の「量子ゲート方式」で、世界的にもこちらを「量子コンピュータ」と呼びます。従来のコンピュータと同じく、人が任意のプログラムを用意して、コンピュータが答えを探す仕組みです。あらゆる分野に活用できると考えられており、実用化に期待がもたれています。
もう1つの「量子アニーリング方式」は、たくさんの組合せの中から最適なものを選び出す、いわば「組合せ最適化計算」に特化したもので、「特化型」と表現されることもあります。ハードウェアへの実装の難易度が幾分低く、実用度もこちらがリードしています。
量子コンピュータにも得意・不得意がある
量子コンピュータは、従来のコンピュータでは不可能だった、超高速な並列計算を可能にします。しかし、すべての分野において圧倒的な性能を発揮するものではありません。従来のコンピュータと比較して高速化するものは、機械学習や量子シミュレーションをはじめとした100程度に限られると考えられています。
機械学習が含まれていることからもわかるように、特に人工知能(AI)の開発には非常に役立つと考えられており、また、創薬や金融などの分野にもブレイクスルーを起こすとされています。実際、すでに金融機関などを中心に、量子コンピュータ活用の検討はスタートしているようです。
一方で、量子コンピュータは四則演算が苦手です。そのため、例えば表計算ソフトは高速化できないと考えられています。こうした特性から、すべてが量子コンピュータに置き換わるのではなく、従来型のコンピュータが苦手な部分を量子コンピュータがカバーする使われ方がされていくでしょう。
量子コンピュータの現在地

量子コンピュータは現在どのような状態にあり、実用化にどれくらいの時間がかかるのでしょうか。ここでは、最新の量子コンピュータの実力や、抱えている課題などを解説します。
量子コンピュータを開発している団体・企業
現在(2024年5月)、量子コンピュータでもっとも先行しているのは、2023年12月に新プロセッサ「IBM Quantum Heron」を発表した米国のIBMです。
米国では他にも、世界最大手のCPU/MPUメーカーであるインテルや、Googleを擁するアルファベット、電子制御システム大手ハネウェル(量子コンピュータは「Quantinuum」)、量子コンピュータ開発企業IonQ(イオンキュー)などが開発を行っており、世界の最先端を行っています。
日本では、2023年3月に初の国産量子コンピュータ「叡(えい)」が発表されました。これは、理化学研究所と富士通が共同で設立した「理研RQC – 富士通連携センター」によって開発されたものであり、2024年には倍以上の性能をもった新型機が発表される予定もあります。
なお、国産量子コンピュータ「叡(えい)」の開発に携わった企業としてNTTが挙げられるほか、IBMの量子コンピュータ開発にはJSRや三菱ケミカルが携わっています。さらに、NECは東北大学と共同で、「量子アニーリング方式」のマシン開発を進めています。
現在の量子コンピュータの実力は?
従来のコンピュータに比べて、超高速での並列計算が可能となる量子コンピュータですが、少なくとも現段階で、従来のスーパーコンピュータを超えるような能力は実現されていません。
その理由は「量子ビット数」にあります。現在のスーパーコンピュータの能力を凌駕するには、ざっくりと「100万量子ビット」程度が必要と考えられています。しかし、前述の「叡(えい)」が64量子ビット、IBMの「IBM Quantum Heron」が133量子ビットと、まだまだ世の中が期待するような性能は発揮できないことがわかります。
しかし、量子ビット数に関して悲観することはないでしょう。理化学研究所の1号機が64量子ビット、2024年に登場が予定されている新型機が144量子ビットであることからもわかるとおり、量子ビットの数は指数関数的に増加していっています。現状のペースが維持されれば、2030年頃には100万量子ビット級の量子コンピュータが実現するはずです。
出典:量子ビット数2倍以上…理研が開発する量子コンピューター国産4号機の性能|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
量子コンピュータの発展に必要な「熱流入問題」の解決
量子コンピュータは、2030年頃の100万量子ビット達成を目指して開発が進められています。しかし、現状の開発ペースを維持していくと「熱流入問題」という大きな課題にぶつかります。
量子コンピュータを動作させるには、-273℃(絶対温度零度)程度の環境が必要になり、そのためには特殊な「希釈冷凍機」が必要です。しかし、仮に量子コンピュータが100万量子ビットを達成すると、その大きさはワンルームマンションの1室程度になってしまいます。
そして、希釈冷凍機の中にある量子コンピュータチップと、冷凍機の外にある制御機器とをつないでいる金属ケーブルを伝って、冷凍機の中に室温が伝わってしまう問題もあります。特に、ワンルームマンションほども巨大な量子コンピュータとなれば、金属ケーブルも大量に必要となるため、伝わる熱も相当な量と考えられます。
この「熱流入問題」を解決するために、低温で動作する超伝導デジタル回路の開発や、制御機器の小型化など、さまざまな技術開発が行われています。しかし、今後技術的なブレイクスルーが起こらなければ、量子コンピュータの進化は頭打ちになるでしょう。
量子エラー訂正に関する技術の開発も不可欠
量子コンピュータは、その動作の中でエラーが発生します。エラーは演算能力に影響するため、検出して訂正する必要があります。しかし、この量子エラーを訂正する技術がまだ確立されていないことも課題です。
実用的な量子エラー率は、甘く見積もっても0.0001%程度までに抑えなくてはいけないと考えられています。しかし、これまでの量子エラー率は0.1%程度であり、3桁以上違う状況です。このことからも、エラー訂正技術の開発が急務であることがわかるでしょう。
研究は進められており、2023年2月にはGoogleが量子エラーの訂正に成功。訂正のために使用する量子ビットを増やしていくことで、実用的なレベルまでエラー率を下げられる見込みであると発表しました。
また、2023年12月には、ハーバード大学が、QuEra Computing、MIT、NIST/UMDと連携して行った実験において、量子エラーを訂正する大規模アルゴリズム実験に成功したと発表しました。
量子エラー訂正に関する技術の開発は、まだ最初の一歩を踏み出したばかり。いち早く訂正技術が確立されることが肝となるでしょう。
出典:Suppressing quantum errors by scaling a surface code logical qubit|Google Research
出典:Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays|nature
量子コンピュータの実用化で起こり得る倫理的課題も
量子コンピュータが実用化されると、倫理的な問題が起こることも考えられます。代表的な例は、既存のサイバーセキュリティを脅かす可能性があることです。
「量子アニーリング方式」の量子コンピュータは、たくさんの組合せの中から最適なものを選び出すことに特化しています。つまり、これまでできなかったようなパスワード解析や、暗号化された情報の解読が可能になる可能性が高いのです。
現在、インターネットを介して行われるさまざまな取引は、こうした暗号化技術に依存しています。そして、ビットコインに代表されるブロックチェーン技術も同様です。しかも、「量子アニーリング方式」は比較的実用化が早いことが想定されており、脅威はすぐそこまで迫っているのかもしれません。
まとめ
量子コンピュータは、量子力学の不思議な原理を利用した革新的な技術です。現在は2030年に100万量子ビットを達成することを目指して開発が進められていますが、熱流入問題や量子エラー訂正などの技術的障壁も残されています。
しかし、一度その扉が開けば、AIや機械学習、金融などの分野でブレイクスルーを起こすと考えられています。最先端の量子コンピュータ技術の進歩に、今後も大きな注目と期待が寄せられています。
掲載日:2024年8月9日