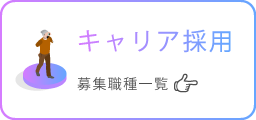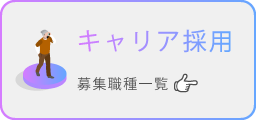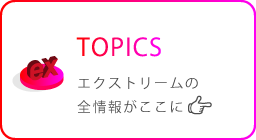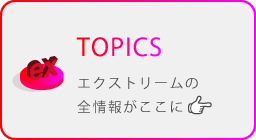開発現場のエンゲージメントを高める「ゲーミフィケーション」とは?基本や実践の流れを解説
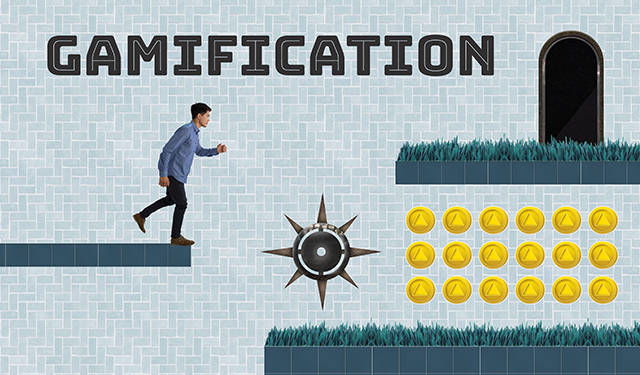
リモートワークの普及や開発の高速化が進んだことで、日々の業務に追われてチームの一体感が希薄になったり、メンバーのモチベーション維持が難しくなったりするケースは少なくありません。ITエンジニアの生産性やチームのパフォーマンスをいかに高めるかは、多くの企業にとっての共通の課題です。
そこで注目されているのが「ゲーミフィケーション」というアプローチです。ゲームが持つ「人を夢中にさせる」仕組みを業務に応用することで、メンバーの主体性を引き出し、チーム全体のパフォーマンスを向上させることが期待されています。
ここでは、ゲーミフィケーションの基本的な概要から、開発現場で活用するメリット、具体的な導入の流れ、失敗しないための注意点などを解説します。
ゲーミフィケーションとは?
まずは、ゲーミフィケーションの概要と、その背景にある考え方から解説します。
ゲーミフィケーションの概要
ゲーミフィケーションとは、ゲームのデザイン要素や原則を、ゲーム以外の分野(ビジネス、教育、健康など)に応用して、モチベーションやエンゲージメントを高める手法のことです。
重要なのは、単に業務を「ゲームのように見せる」こと(Game-like)が目的ではないことです。娯楽を目的とするのではなく、あくまで「コードレビューを活性化させる」などの、ビジネス上の課題解決を目的としています。
なぜゲームの仕組みが有効なのか
ゲーミフィケーションが効果を発揮する背景には、人間の心理や脳の仕組みが関係しています。
脳の「報酬システム」の活用
人間は目標を達成したり、他者から承認されたりすると、脳内で「ドーパミン」という神経伝達物質が分泌されます。これは快感や意欲をもたらす脳の「報酬システム」として機能するものです。
ゲーミフィケーションは、ポイントの獲得やバッジの授与といった仕組みを通じて、この報酬システムを意図的に刺激し、「もっと頑張りたい」という動機付けを促すものです。
行動経済学の応用
行動経済学では、人間は必ずしも合理的に行動するわけではなく、ちょっとした後押し「ナッジ(Nudge)」によって行動が変容することが知られています。
ゲーミフィケーションは、トップダウンの強制的なルールではなく、「つい参加したくなる」ようなナッジを設計することで、メンバーの自発的な行動を自然に引き出すアプローチと言えます。
開発現場におけるゲーミフィケーションのメリット
ゲーミフィケーションを開発現場に導入すると、どのようなメリットが期待できるのでしょうか。ここでは代表的な3つのメリットを紹介します。
貢献度が可視化されモチベーション向上につながる
日々の開発業務では、コードレビューでの丁寧な指摘や、ドキュメントの整備、他のメンバーへのサポートといった、直接的な成果として現れにくい業務が多く存在しています。ゲーミフィケーションは、こうした見えにくい貢献にポイントやバッジを与えることで、個々の貢献を可視化できます。
チームへの貢献が認められ、評価されることで、エンジニアは仕事に対する達成感をより強く感じられるようになり、仕事へのモチベーション向上につながります。
主体的な行動を促進する
重要ではあるものの緊急性が低いタスクを、「期間限定クエスト」や「チャレンジイベント」として設定することで、メンバーが主体的に取り組むきっかけを作れます。
「技術的負債の返済」や「テストカバレッジの向上」といった後回しにされがちな業務を、「やらなければならない作業」から「クリアしたい挑戦」へと意味付けを変えることで、イヤイヤ行うのではなく、ポジティブな雰囲気で問題を解決できるようになります。
チームワークとコミュニケーションの活性化
ゲーミフィケーションの設計次第で、個人間の競争だけでなく、チームでの協力を促進することも可能です。例えば、チーム単位でポイントを競う「チーム対抗戦」や、全員で協力して目標達成を目指す「協力クエスト」などを導入します。
共通の目標に向かって協力する過程で、メンバー間のコミュニケーションが自然と活発になります。特にリモートワーク環境では希薄になりがちな横のつながりを強化し、チームとしての一体感を醸成する効果が期待できるでしょう。
新人エンジニアの育成に役立つ
ゲーミフィケーションは、新人エンジニアの研修や育成においても有効です。覚える知識やスキルが多く、ハードルの高さを感じやすい初期段階で、ゲーム的な仕組みがモチベーションの維持に役立ちます。
例えば、「連続学習日数」で特別なバッジを与えたり、チーム対抗で課題の達成率を競うことで、楽しみながら学習を継続する動機付けになるでしょう。
また、仕組みが動機付けとなる体験をすることで、「ユーザーがなぜこの機能を使うのか」といった心理的な視点を養うことにもつながります。将来的に、UX設計やプロダクト開発で求められるユーザー思考の基礎を育むことにもつながるでしょう。
ゲーミフィケーションを実践する具体的な流れ
ゲーミフィケーションの導入に、大規模なシステムは必須ではありません。スモールスタートが成功の鍵です。具体的な流れを解説します。
ステップ1.解決したいことを明確にする
最初に、チームが現在抱えている課題の中から、ゲーミフィケーションで解決したい目的を明確にします。目的を具体的に設定することで、ルール設計がしやすくなり、導入後の効果測定もしやすくなります。
【目的設定の例】
課題: コードレビューの依頼が滞りがちで、指摘も形式的なものが多い
目的: コードレビューの質と速度を向上させ、活発な議論が生まれる状況を作る
ステップ2.ルールと報酬を決定する
設定した目的に沿って、評価対象となるアクションやポイントの配分、そして報酬(リワード)を決定します。大切なのは、ポイント稼ぎそのものが目的化しないよう、チームの価値向上につながる行動を評価することです。
なお、最初から金銭的なインセンティブは設定せず、まずは称賛やチームへの還元といった非金銭的な報酬から始めるのが安全と考えられます。
【ルール設計の例】
・依頼から24時間以内に最初のレビューを実施:10pt
・バグ発見や設計改善につながる指摘:20pt など
【報酬(リワード)の例】
・Slackプロフィールなどで使える「今月のレビューマスター」といった称号バッジを授与
・貯めたポイントを使って勉強のための書籍を購入できる
ステップ3.ツールで可視化・自動化する
設計したルールを運用するための仕組みを構築します。手作業での運用は担当者の負担が大きく、また形骸化しやすいため、可能な限り自動化することが継続の秘訣となります。
手軽に始めるなら「スプレッドシート」
最も簡単な方法は、Googleスプレッドシートなどを使って手動でポイントを集計し、週次ミーティングなどでランキングを発表することです。自動化としては十分ではありませんが、これだけでも十分にゲーム感覚を醸成でき、スモールスタートしやすい方法です。
本格的な運用には「GitHub Actionsとチャット連携」
ゲーミフィケーションが軌道に乗ったら、GitHub Actionsなどを活用することで運用を自動化するとよいでしょう。
例えば、プルリクエスト上でのレビューコメントや承認といったアクションをトリガー(きっかけ)としてポイントを計算し、結果をSlackやDiscordなどのチャットツールに通知する仕組みを構築する方法などが挙げられるでしょう。
クラウドサービスには、こうした自動化のための機能が提供されているケースがあり、例えば「誰かがレビューをしたら自動でSlackに通知し、スプレッドシートのポイントを更新する」といった一連の流れを比較的簡単に自動化できます。
ゲーミフィケーション導入時の注意点
ゲーミフィケーションは強力な手法ですが、設計や運用を誤ると逆効果になる可能性があります。ここでは、導入時に注意すべきことについて解説します。
過度な競争が起こってしまう
個人のポイントやランキングを強調しすぎると、ポイントのために他者のレビューの粗探しをしたり、簡単なタスクばかりを選んだりといった、意図しない行動を誘発しかねません。
競争意識が行き過ぎてしまい、メンバー間の協力関係が損なわれるリスクを減らすため、個人だけでなくチーム単位での目標を設定したり、他者への貢献(ヘルプやサポート)を評価項目に加えるなど、協力を促すルール設計を心がけることが重要です。
「やらされ感」が発生してしまう
ゲーミフィケーションが新たな「ノルマ」や「管理ツール」として認識されてしまうと、メンバーは「やらされ感」を抱き、自発性を失います。ゲームは、あくまで自発的に参加するからこそ楽しいものです。
ルール設計の段階からメンバーを巻き込み、納得感のあるルールを作り上げるプロセスが不可欠です。また、定期的にルールの見直しを行い、形骸化していないか、不公平感が出ていないかを確認することも大切です。
純粋な動機を阻害してしまうことがある
報酬やペナルティといった動機付けは、使い方を誤ると、エンジニアが元々持っている「良いものを作りたい」「知的好奇心を満たしたい」といった純粋な動機を阻害してしまう可能性があります。
報酬がないと行動しなくなることを避けるために、報酬をあくまで「感謝のしるし」や「貢献の可視化」の手段と位置づけ、仕事そのものの面白さや、スキルアップの実感を損なわないバランスを保つことが大切です。
まとめ
ゲーミフィケーションは、開発現場におけるつながりや、生産性の課題を解決するための有効な選択肢の一つです。健全な競争や達成感、協力といったポジティブな要素を組み込むことで、業務を活性化できます。
一方で、ゲーミフィケーションは万能薬とは言えず、チームの文化や課題に合わせた設計が求められます。導入そのものを目的にするのではなく、あくまでチームをより良くするための手段と捉えることが重要でしょう。
今後、エンジニアリング組織のマネジメントにおいて、こうした心理的アプローチの重要性は高まっていくものと考えられます。あなたのチームでも「仕事を楽しむ」ための仕組みづくりを考えてみてはいかがでしょうか。