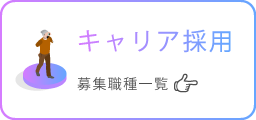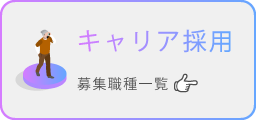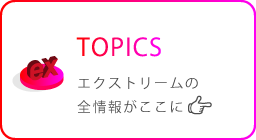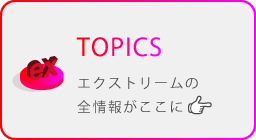GraphQLとは? RESTとの違いやメリット・デメリットも解説
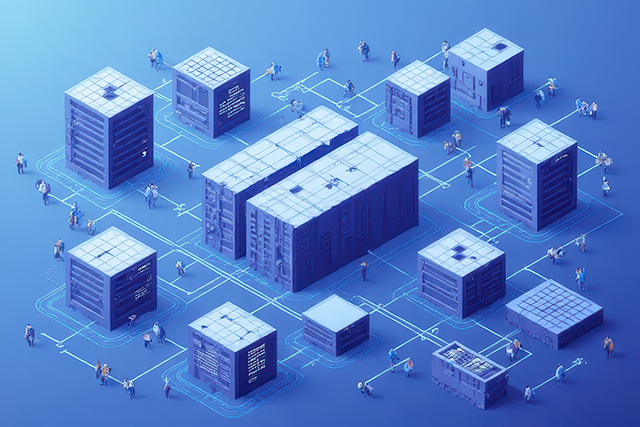
近年、Webサービスやアプリケーション開発において、フロントエンドとバックエンド間のデータ通信を効率化する技術として「GraphQL」が大きな注目を集めています。
今回は、「GraphQL」とは何かという基本から、従来広く使われてきた「REST API」との違い、メリット・デメリット、さらには導入に適したケース・不向きなケース、そしてその将来性までを詳しく解説します。
GraphQLとREST APIの違い
GraphQLとRESTは、どちらもAPI(アプリケーション間で情報をやり取りするための仕組み)を設計するための手法です。しかし、そのアプローチには本質的な違いがあります。
アーキテクチャとデータ操作
RESTとGraphQLは、APIの基本構造が対照的です。RESTは情報の種類ごとに個別のアドレス(エンドポイント)を用意しますが、GraphQLは一般的に通信の窓口を一つに集約します。
RESTではデータ取得において各アドレスから固定のデータが返されますが、複数回の通信が必要になりがちです。一方、GraphQLは、クライアントが必要なデータ構造を細かく指定し、一度の通信で過不足なく情報を得られます。より効率的といえるでしょう。
操作方法も異なり、RESTが通信規格で定められた「取得」や「更新」といった操作を使い分けるのに対し、GraphQLは要求文そのものに操作内容を記述して送信する方式を取っています。
開発を支える技術とトレードオフ
GraphQLは、APIの厳密な「設計図(スキーマ)」が必須となり、これにより安全な開発が保証されることが強みといえます。RESTの場合、外部ツールで補う必要があります。
エラーの表現も異なり、RESTが通信規格のコードで成否を示すのに対し、GraphQLは通信が成功してもレスポンス内でエラーを返し、「部分的な成功」といった柔軟な状態を表現可能です。
トレードオフもあります。RESTは標準の仕組みで通信結果を一時保存(キャッシュ)しやすい一方で、GraphQLは通信方式の違いから同様のキャッシュが難しいため、クライアント側での適切な設計・対策が求められます。
エコシステムと技術の成熟度
RESTは長年の利用実績があることから、巨大なコミュニティがあり知見の交換も活発です。ツールも豊富なため、安定した技術と位置づけられるでしょう。
2015年に公開されたGraphQLは比較的新しい技術で、公開当初はツールも少ない状況でした。しかし、2025年現在は「Apollo、Hasura」「AWS AppSync」などのフレームワークやSaaSが充実し、一般的な開発要件はほぼ網羅されています。
GraphQLのメリット
GraphQLが多くの開発現場で採用されているのは、それがもたらす多くのメリットによるものです。ここでは、その主な長所を整理します。
必要なデータだけを取得できる
GraphQL最大の利点は、クエリで指定したデータ項目のみがレスポンスとして返ってくることです。
REST APIで起こりがちな、エンドポイントが固定されているために不要なデータまで取得してしまう「オーバーフェッチ」や、逆にデータが足りずに追加のAPI呼び出しが必要になる「アンダーフェッチ」といった問題を解消できます。
結果として、モバイルネットワークのような通信帯域が限られる環境でも、データ転送量を最小限に抑え、アプリケーションの応答性を高められます。
一度のリクエストで複数のリソースを取得できる
GraphQLでは、関連する複数のデータ(リソース)を単一のクエリでまとめて取得できます。
例えば、ユーザー情報と、そのユーザーの投稿一覧を一つの画面に表示したい場合、RESTでは別々のエンドポイントへ複数回リクエストを送ります。しかし、GraphQLなら一度のリクエストで両方のデータをまとめて取得可能です。
これにより、ネットワークの往復回数を削減できるため、通信遅延が大きい環境下における表示速度が向上します。
厳密な型システムによるスキーマ駆動開発
GraphQLは「スキーマ」と呼ばれる設計図に基づいてAPIの仕様を厳密に定義します。このスキーマにはデータの型が明確に定められており、リクエストとレスポンスの食い違いが発生しにくくなります。
この特性によりバグを早期に発見できるほか、このスキーマを「信頼できる唯一の情報源(Single Source of Truth)」として、フロントエンドとバックエンドのチームが並行して開発を進める「スキーマ駆動開発」を実践しやすくなります。
豊富なエコシステムと開発者ツールの充実
GraphQLは比較的新しい技術ですが、そのエコシステムは急速に拡大しています。
スキーマから型定義やコードを自動生成するツール(GraphQL Code Generatorなど)、クエリを試せる開発環境(GraphiQLなど)、パフォーマンス監視ツールなど、開発を支援する多彩なツールが揃っています。
特に、APIの仕様自体が自己記述的であるため、ドキュメントを自動生成しやすく、従来のAPI開発で大きな負担となりがちだったドキュメント整備の手間を大幅に軽減できます。
こうしたメリットにより、開発時の生産性を高めます。
バックエンド・フロントエンドの分離開発
GraphQLでは、原則としてAPIのエンドポイントは一つです。そのため、新しい画面要件が生まれるたびに専用のエンドポイントを追加する必要性を減らせます。
バックエンドの変更を待つことなく、必要なデータをクエリで組み合わせて取得できるため、フロントエンド開発者が主導権を持って開発を進められます。
また、APIの拡張も容易で、スキーマに新しいフィールドを追加するだけで、既存の機能を壊さずにAPIを進化させられます。
GraphQLのデメリット
便利なGraphQLですが、一方で導入や運用には注意すべき点も存在します。ここでは、GraphQLが持つデメリットや課題について解説します。
学習コストと実装の難易度が高い
GraphQLを導入する際は、スキーマ設計、QueryやMutation、Resolver、データローダーといった、GraphQL特有の用語や技術を新たに理解する必要があります。
特に「スキーマ設計」は、多くの知識と時間を要する重要な工程です。そのため、特にチーム内に経験豊富なメンバーがいない場合、複雑なアプリケーションをGraphQLで構築するまでの学習コストは高くなりがちです。
柔軟なクエリがセキュリティリスクにつながることがある
GraphQLの柔軟なクエリは、セキュリティリスクにもつながることもあります。
スキーマ情報が公開されていると、悪意のある第三者から攻撃を受ける可能性があり、サーバーに過剰な負荷がかかることや、意図しないデータ漏洩につながる危険性が否定できません。
導入する際は、クエリの深さや取得できるフィールド数に上限を設けたり、アクセス制御を厳密に行ったりするなど、適切な防御策を講じる必要があります。
応答時間が長くなるケースがある
GraphQLでは、一度のクエリで必要なデータをまとめて取得する設計を行うため、データを集約する処理が複雑になり、結果として応答時間が長くなりがちです。
REST APIではリソース単位で個別にデータを取得するため、各レスポンスは軽量ですが、GraphQLは単一のリクエストで多くのデータを集約するため、処理時間が長引き、画面表示までにタイムラグが生じることがあります。
モニタリングとエラーハンドリングの複雑さ
GraphQLでは、すべてのリクエストが単一のエンドポイントに集中します。そのため、エンドポイントごとに応答時間やエラー率を計測する従来の方法が適用しにくく、ボトルネックとなっている箇所を特定することが困難です。
この問題を解決するために、ログに含まれるクエリ内容の解析や、APM(Application Performance Management)ツールを導入するなどの対策が必要になります。
小規模アプリは導入コストに見合わないことがある
高度なデータ取得が求められないシステムにとって、GraphQLの機能が過剰になる場合があります。
例えば、REST APIで十分に対応できる小規模サービスの場合、GraphQLを導入することで、スキーマ設計やResolverの実装といったコストが見合わず、かえって開発効率を下げてしまう可能性が考えられます。
GraphQLの向き・不向きとは?
RESTとの違いやメリット・デメリットを踏まえ、GraphQLの向き・不向きについて解説します。
【向いている用途】複雑なデータを扱うアプリ
SNSのフィードや多機能なダッシュボードのように、一つの画面を表示するために多数のAPI呼び出しが発生する状況で、GraphQLはその力を発揮します。
一度のクエリで必要な情報をまとめて取得できるため、特に通信環境が不安定になりがちなモバイルアプリなど、ネットワーク通信の回数を最小限に抑えたいケースでも大きな恩恵を受けられるでしょう。
【向いている用途】クライアントごとに必要なデータが異なるケース
Webブラウザやモバイルアプリ、IoTデバイスなど、同じバックエンドを利用するクライアントごとに、必要とするデータの種類や粒度が異なるケースがあります。
そういったケースでGraphQLを導入すると、クライアント側が欲しいデータだけを選んで取得できるため、APIの再利用性が向上します。
これにより、汎用的なGraphQL APIを一つ用意するだけで、クライアントは自身の要件に合わせてクエリを組み立て可能となるため、クライアントごとにAPIを個別開発する手間が省けます。
【向いている用途】迅速なUI変更・試行を行う開発
アジャイル開発などで、フロントエンドのUI/UXを素早く改善していきたい場合にも、GraphQLは適しています。
新しい画面要件に合わせてAPIの仕様変更が必要になっても、GraphQLであれば既存のスキーマにフィールドを追加するだけで対応できることが多く、バックエンド開発者の負担が軽減されます。
また、フロントエンドチームの裁量で柔軟にデータを取得できることから、プロトタイピングやA/Bテストも実施しやすくなります。
【向いている用途】複数のデータソースを統合したいケース
マイクロサービスアーキテクチャのように、機能ごとにデータソースが分散しているシステムにおいて、それらを統合する役割としてもGraphQLは強力な働きをします。
例えば、ユーザー情報サービス、注文履歴サービス、在庫サービスなどに個別に問い合わせる代わりに、GraphQLゲートウェイがそれらの結果を集約し、クライアントには単一のAPIとして提供する構成が可能です。大規模な組織でもサービスを横断した柔軟なデータ取得基盤を構築できるでしょう。
GraphQLに不向き、または慎重な検討が必要なケース
GraphQLは、以下のようなケースにおいて導入コストがメリットを上回ると考えられます。解決したい課題と既存の資産を天秤にかけて、GraphQLが本当に価値を生むかどうかを慎重に見極めることが重要です。
APIの要件がシンプルなケース
扱うデータが少ない単純なアプリケーションでは、RESTの方が向いています。GraphQLの学習コストや設計の複雑さを考慮すると、メリットを享受しにくいでしょう。
既存のREST中心のインフラが安定稼働しているケース
REST APIを前提としたキャッシュ、認証、モニタリングの仕組みがすでに安定稼働しているケースでは、それらをGraphQLに合わせて再設計するコストが非常に高くなると考えられます。
不特定多数に公開するAPIで、厳密な料金計算や利用制限が必要なケース
従量課金制の公開APIなどでは、リクエストの自由度が高いGraphQLは注意が必要です。取得データ量やサーバー負荷が変動することから、料金計算や利用制限の設計が難しくなります。
GraphQLの将来性とエコシステムの動向
GraphQLは、公開から約10年でMeta(旧 Facebook)、GitHub、Shopify、Netflixといった多くの企業に採用されました。今後、世界中のさらに多くの企業がGraphQLを利用すると予測されており、特に乱立したAPIを統合したい大企業で導入が加速すると考えられます。
一方で、RESTが完全にGraphQLに置き換わるわけではなさそうです。多くの企業では、システム内部の通信にはRESTやgRPCなどを引き続き利用し、外部公開用のAPIや複数サービスを統合するレイヤーにGraphQLを採用する、「併用戦略」を行っています。
金融、Eコマース、IoTなど、GraphQLが活用される分野は着実に広がっており、セキュリティ監査やクエリコストの可視化を支援するSaaSも登場しています。こうしたエコシステムの発展を踏まえると、今後さらに存在感を強めていくと予想されます。
まとめ
GraphQLは、クライアントが必要なデータを柔軟かつ効率的に取得できる、強力なAPI技術です。一度の通信で過不足なくデータを取得できるため、特に複雑なUIを持つアプリケーションや、複数のデータソースを扱うシステムにおいて大きなメリットを発揮します。