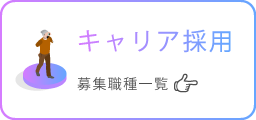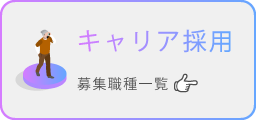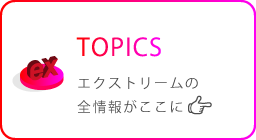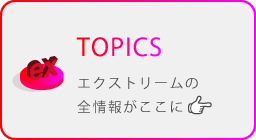厳しく見られる時代に合わせた成長を
最新事例とともに考える、eスポーツ業界のコンプライアンス事情
近年、芸能人やスポーツ選手など公共性の高い立場の人物に関して「コンプライアンス」が問題となることが増えています。
「コンプライアンス」は元々「法令遵守」を意味する言葉であり、従前は企業の行いが法令に反していないか取り締まる目的で使われていましたが、広く浸透するに連れて「社会通念上にそぐわない、倫理に反する言動」全般に厳しい目が向けられています。
その適応範囲も広がっており、企業や組織などの所属の有無に関わらず、個人でも言動に配慮が求められる風潮は強まり、公的な場での発言以外にも、SNS上での投稿なども取り沙汰されるようになっています。

今ではインフルエンサーとして影響力が強いeスポーツ選手やストリーマーもそうした目を向けられる立場に並んできていると言えるでしょう。
今回は、昨今のeスポーツ界で起こったコンプライアンスにまつわる事例を振り返りながら、その背景と対策を考えます。
SNS上や配信の言動に対する視線はより厳しく
著名なeスポーツ選手による配信上での発言やSNSへの投稿が問題となり謹慎処分や契約解除となるケースは、過去から何度も発生してきた「起こりやすいコンプライアンス違反」の代表例と言えます。
ここ数年では「発言に気を付けるべき」という意識も強まってきており、そうしたケースは減少しつつありますが、残念なことに印象的な事例はまだ発生しています。
2025年5月には、あるFPSタイトルの世界大会で日本チームに敗れた海外チームの選手がSNSに「キノコ雲」の写真を投稿した件が大きな問題となりました。
選手はすぐに謝罪し、あくまで試合に負けてしまったことに対する感情の表現として爆発の画像を用いたものであり、歴史的背景の認識不足が招いた事態で攻撃的な意図はなかったと説明。チームとしても公式な謝罪声明を行い、該当選手の減俸や全選手およびコーチ陣に向けた再教育プログラムの実施を発表しましたが、6年間チームと協業してきた日系企業は「価値観に一致しない」としてスポンサーを降りる結果となってしまいました。
本件は投稿が国際的に問題視されるような内容だったこともあり、これだけ大きな影響を招いてしまったことも致し方ないと感じられるかもしれません。しかし、コンプライアンス意識が高まる昨今は、スポンサー企業としても「問題を起こした選手が所属しているチーム・組織をサポートしている」と見られることのリスクも高まっています。本人が十分な罰則を受けたか否か、あるいは悪意の有無に関わらず、問題が発生した場合にはそれまでの関係性を維持することは非常に難しい情勢となってきていると言えるでしょう。
入国管理問題で分かるeスポーツの広まりと知識の重要性
別のケースでは、日本人プロ選手がアメリカでの大会出場のために渡航したものの、入国管理にてその目的を正しく伝えられず、思わず「観光に来た」と伝えてしまい、その旨をSNSに投稿までしてしまうという事態が発生しました。結果、所属チームは選手の出場を取りやめを判断し、選手を急遽帰国させざるを得ない結果となってしまいました。
このケースでは大会の結果によって賞金を受け取る可能性があり、現地で税務が発生し得る状態であることを考えても「観光」という入国理由は不適切でした。入国にまつわる問題意識の不足から状況をSNSに投稿してしまった点も含め、チームとしても選手をそのままアメリカで大会に出場させる訳にはいきませんでした。

もちろん、英語で入国目的を正しく伝えられる語学力を身に着けることはグローバルでの活躍を視野に入れるためにも望ましいことですが、英語圏以外で大会に出場することも珍しくなくなっている以上、コミュニケーションが難しい地域への入国は今後も起こり得るものです。
プロチームも所属選手が海外大会に参加する際には、チーム側も航空券や現地ガイドの手配などさまざまなサポートの手段を尽くしていますが、今後は入国管理を独力で正確に乗り越えられるような事前の対策についても求められるようになってくるでしょう。
eスポーツと入国を巡っては、まだ世間にeスポーツが広まる以前は「ゲームの大会に出場するために来た」と伝えても理解されず入国に苦労したというエピソードが語られることもありましたが、まさに時代の変化を象徴するような出来事になりました。
独自の魅力を保ったままの成長に期待
eスポーツ界は年齢層が若く社会経験が少ないプレイヤーも多いため、黎明期からさまざまなコンプライアンス問題に直面し、その度に少しずつ業界全体で知見を共有しながら前へと進んできました。
過去には他のスポーツと同様にコーチと選手間でのハラスメントが問題となったこともあれば、「プロ選手が一緒にゲームをプレイした“フレンド”のゲーム内ネームが差別的な言葉であった」という事態が選手の活動自粛に繋がったこともあり、特殊性の高い業界が故に多様なシチュエーションが発生してきました。
2025年6月には日本有数の大規模プロeスポーツチーム「FENNEL」が外部講師を招いて全所属メンバーに対するコンプライアンス研修を行うなど対策意識も高まってきており、昨今の新たな事例から学びを得ながら、より魅力的で安心できる業界へと成長していくステップが訪れています。
何かと槍玉にあがるSNSの存在ですが、ゲーム内やSNS、配信を通じて選手とファンが交流しやすい距離の近さはeスポーツの魅力のひとつ。何もかも“禁止”による対策を講じるのではなく、eスポーツらしい楽しさを誰もが共有できる状態での成長を期待したいと思います。