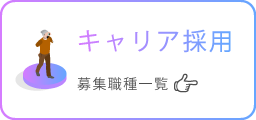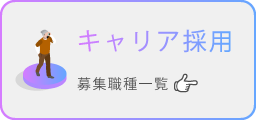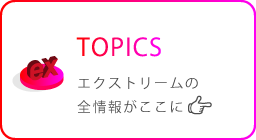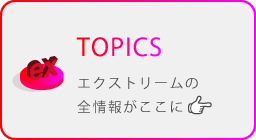ITエンジニアこそ取り組みたい「デジタルデトックス」のすすめ

デジタルデバイスが生活の一部となった現代、多くの人がデジタル機器の使い過ぎによる健康への影響を受けています。中でも、ITエンジニアはデジタル機器に触れる時間が特に長く、影響を受けやすい職業と言えるでしょう。
そこで注目したいのが「デジタルデトックス」です。意識的にスマートフォンやパソコンから距離を置くことで、心と身体をリフレッシュさせます。ここでは、効果や実践方法を解説し、デジタル機器と適切に付き合い、パフォーマンスを向上させる方法を紹介します。
デジタルデトックスとは
デジタルデトックスとは、スマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイスから距離を置いてストレスを軽減し、現実世界での体験や人との交流を大切にしようとする取り組みのことです。
デジタルデトックスを推進する日本デジタルデトックス協会によれば、デジタルデトックスにより次のような効果が得られるとしています。
デジタルデトックスの効果
・気持ちがスッキリする ・目の疲れが取れる ・頭(脳)の疲れが取れる ・睡眠の質が良くなる ・ストレスが減る ・安心感が増す ・想像力(創造力)が高まる ・ひらめきが良くなる ・五感がさえる ・幸せな気持ちになれる
|
現代の生活において、デジタルデバイスは必要不可欠です。しかし、過度な依存によって、仕事のパフォーマンスが低下することや、健康に悪影響を与えることも少なくありません。デジタルデバイスと適切な距離で付き合う方法として注目されています。
デジタルデトックスが注目される理由は深刻なスマホ依存

デジタルデトックスが注目されるようになったのはなぜでしょうか。それは、スマートフォンの普及により、常にインターネットとつながっている状態になったことが理由として挙げられます。
2024年にシチズンが行った、全国のビジネスパーソン400人を対象とした調査では、1日のスマートフォンの平均使用時間が3時間以上の人が約半数を占め(53.6%)、5時間以上のヘビーユーザーも約20%いることがわかっています。
特に、SNSや動画プラットフォームは、ユーザーの興味を引くコンテンツを提供することで利用時間を延ばし、企業の利益に直結する仕組みが作られています。そのため、多くの人が無意識のうちに依存してしまうのです。
デジタル機器の使い過ぎで起こる問題はいくつかありますが、代表的なものとして、頭(脳)や身体が疲れてしまうことが挙げられ、それによるさまざまな影響も指摘されています。
出典:50 年間の変化で見るビジネスパーソンの生活時間|シチズン
デジタル機器の使い過ぎによる影響とは
日常的に長時間デジタル機器を使用することで、私たちの心身にはさまざまな悪影響がおよびます。
集中力の低下
デジタル機器の使用時間が増えることで、脳が常に新しい情報を求める「情報依存」の状態に陥りやすいと考えられています。
情報依存の状態になると、一つのタスクに集中することが難しくなり、注意散漫や生産性の低下が起こります。仕事や学習中にSNSやスマホなどの通知に気を取られると、脳がマルチタスクを強いられ、さらに疲労が蓄積されるのです。
エンジニアは問題解決に集中することが重要な職種ですが、頻繁なSlack通知や、つい片手間でスマホを開いてSNSをチェックしてしまうクセが、仕事に集中することの妨げになっている可能性が指摘されています。
目の疲れ・身体の疲れ
デジタル機器のモニターを長時間凝視すると眼精疲労の原因となります。PCモニターやスマートフォンと距離が近い場合、目の周りの筋肉が緊張しピントを合わせる力が弱まる場合があるのです。
また、同じ姿勢でデバイスを操作し続けることで、肩こりや腰痛も起こりやすくなります。さらに、首を前に倒した姿勢でスマートフォンを操作することで、いわゆる「スマホ首」になる場合があります。ひどい場合は神経が圧迫されて腕や手がしびれたり、めまいが起こったりするため注意が必要です。
こうした身体の疲れや不調は、エンジニアの生産性に直接影響します。エンジニアは長時間同じ姿勢で座り続けることが多いため、特に健康リスクが高まりやすい傾向があります。
睡眠の質の低下
夜間にスマートフォンやパソコンを使用すると、モニターが発するブルーライトの影響で体内時計が乱れ、睡眠の質が低下します。これは、目からブルーライトが入ると睡眠を促すメラトニンの分泌が抑制されることが理由です。
就寝1時間前にスマートフォンを使う際、ブルーライトを約50%カットするメガネを用いた人と、素通しのメガネを用いた人を比較したでは、ブルーライトをカットするメガネを用いた人のほうが総睡眠時間が長く、途中で目が覚めてしまうことも少ないという結果が出ました。
さらに、ブルーライトをカットするメガネを用いた人のほうが午前中の活動度が高くなるとの結果も出ており、ブルーライトが睡眠の質に影響をおよぼし、睡眠の質が翌日のパフォーマンスに影響を与えることを示しています。
脳の疲れ
デジタル機器を使用することで、脳は常に新しい情報を処理し続けます。絶えず情報をインプットする状態は、脳の前頭前野の「浅く考える機能」を使うことになり、脳は休む暇がなくなり疲れやすくなるのです。
その結果、「脳過労」の状態が続くことになり、記憶力や判断力の低下や、頭痛やめまいなどの身体症状が現れやすくなります。
最近の研究では、ぼんやりと考え事をする行為が脳にとって大変重要かもしれない…ということがわかってきており、そのためにも定期的にデジタル機器から離れ、脳をリフレッシュさせることが重要になります。
メンタル面の不調
SNSやニュースサイトの過剰な使用により、おびただしい情報に触れ、知らず知らずのうちに心身が疲れてしまうことがあります。
その状態でネガティブな情報に触れたり、SNSで他者と比較してしまうようなことがあると、過剰反応を引き起こしメンタル面に影響を与えます。さらにはストレスや不安感、うつ症状の原因になることもあります。
ペンシルバニア大学の研究者が行った実験では、3週間にわたってSNSの利用を1日10分に制限した場合、孤独感や憂鬱さが大きく改善することがわかりました。なおこの実験では、1日あたりのソーシャルメディアの使用は30分程度までが適当であろうと結論づけられています。
出典:No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression
そもそもなぜデジタルデバイスに依存してしまうのか

デジタルデバイスへの依存は、現代の技術進化や社会の構造によって強化されている現象です。その主な理由はどのようなものでしょうか?
いつも手元にあるから
現代人にとってスマートフォンは、24時間365日手元にあるものです。さらにITエンジニアの場合、仕事中はかなりの時間パソコンに触れています。
Slackなど業務上必要な連絡のチェックだけでなく、ふとした瞬間の暇つぶしや調べものにもパソコンやスマートフォンなどのデジタルデバイスを使用してしまい、その積み重ねで使用時間が長くなってしまいます。
脳の「報酬システム」が刺激されるから
SNSの「いいね」や、ソーシャルゲームのクリア報酬などは、私たちの脳に快感を与えるドーパミンの分泌を促進することがわかっています。
この仕組みは脳への報酬システムとして働き、頻繁にデジタルデバイスを使いたくなる衝動を生み出していると考えられています。
インターネット・SNSが依存しやすい構造になっているから
インターネット広告やSNSは、ユーザー個人の過去の閲覧データをもとに、興味関心に合ったコンテンツを次々と提供するように作られています。そのため、ユーザーにとって興味のある情報ばかりが提供されるようになり、それが新しい刺激となって長時間デバイスを使い続けてしまうのです。
X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS、TikTokやYouTubeなどの動画サイトの運営者は、自らの利益になるよう、ユーザーがサービスにより多くの時間を費やすよう設計しています。無意識のうちにデバイスから離れられなくなってしまっている人は少なくありません。
社会的なつながりがあるから
現代社会では、連絡手段や情報収集の多くがデジタルデバイスを介して行われています。そのため、デバイスを使わなければ「取り残される」といった不安が生じ、結果として過剰な使用につながることがあります。
また、ITエンジニアの場合、コミュニケーションツールとしてSlackやDiscordなどを使うことが多く、通知や連絡を見逃さないよう常に気にしてしまう人も多いはずです。結果的に、よりデジタルデバイスを利用する時間が長くなってしまいます。
デジタルデトックスの方法
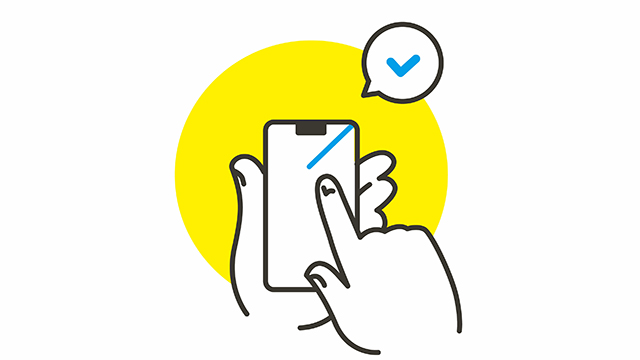
デジタルデトックスを効果的に行うにはどのような方法を取るとよいのでしょうか。ここでは、現実的な4つの方法をご紹介します。
スマホを意図的に遠ざけて目的なく触らない
スマホを常に手元に置いておくと、つい手を伸ばしてしまいます。そのため、意図的に遠ざけることも必要です。
例えば、仕事中はスマホをカバンの中に入れておく、リモートワークであれば別の部屋に置くといった方法があります。使う必要がある時だけ使うようにして、「暇だから」「なんとなく」といった理由でスマホを触る習慣を見直しましょう。
どうしても難しい場合は、ダムフォンと呼ばれる最低限の機能に絞った携帯電話端末を使う方法もあります。しかし、そこまでは難しい人の方が多いでしょう。そんなときは、画面表示をグレースケールにすると良いかもしれません。色からの強い刺激を受けにくくなり、依存性が減る可能性があります。
集中を妨げない通知設定を行う
業務中のメールやSlackの通知で集中力が妨げられないよう、通知設定を工夫しましょう。頻繁に通知が届くと脳は意識をそちらに向けてしまい、集中力を削がれてしまいます。
特にエンジニアは集中を要するタスクが多く、生産性の低下に直結します。かといって、業務中に通知をオフにしてしまうことは現実的ではないでしょう。そこで、通知設定を工夫することがおすすめです。
例えば、iPhoneには決まった時間に通知をまとめて届ける機能があります。Slackには特定の時間のみ通知を受信できるスケジュール機能があります。さらに、どちらも夜間の通知をオフにする機能も備わっています。
これらの機能を活用して、重要なメッセージを見逃すことなく、集中できる時間を確保しましょう。
デジタル機器を使わない日を作る
週末や休日などに、デジタルデバイスをまったく使わない時間を設けてみましょう。自然の中で過ごす、読書やスポーツに没頭するなど過ごし方は様々です。人との対話を楽しんだり、家族や大切なパートナーとの食事を楽しむのもよいでしょう。
自力では難しい場合、「デジタルデトックスツアー」や、宿泊施設がスマホを預かるデジタルデトックスプランを利用する方法があります。半ば強制的に、デジタルデバイスのない環境に身体を慣らすのも方法の一つです。
デジタル機器の使用状況を可視化する
スマートフォンには、自分がどれだけ使用していたか把握できる機能があります。1日の使用時間や、一週間の平均使用時間などが可視化でき、どのアプリをどのくらい使っていたかもわかります。
自分がどのアプリにどれだけ時間を費やしているかを知ることで、何かしらの気づきが得られるはず。そこから、自分に合わせたデジタルデトックスを考えることが成功への近道となるでしょう。
なお、iPhoneでは「スクリーンタイム」、Androidでは「デジタルウェルビーイング」がこの機能にあたり、これらには画面を見ない時間を設定して通知を送る機能なども含まれています。
デジタルデトックスにはデメリットもある?
デジタルデトックスにはデメリットもあります。代表的なものは次の三つです。
初期段階でのストレス
デジタルデバイスへの依存が強い人ほど、スマホが使えないことにストレスを感じるはずです。しかし、この症状は時間と共に緩和されます。無理のない範囲で少しずつ取り組むことが重要です。
連絡頻度が下がることの不安感・孤立感
SlackやLINE、SNSの返信が遅れることで、情報から取り残され、孤立してしまうと感じる人は少なくありません。
連絡に対するレスポンスが落ちることは事実ですが、急ぎの連絡手段を確保しておけば、ほとんどのことは問題にならないはずです。
デジタルデトックスに興味を持っている人は、何かしらの問題や不安を抱えているはず。諦めず、自分にとってちょうど良いデジタル機器との付き合い方を見つけていきましょう。
現代社会における不便さ
現代はキャッシュレス決済の多くがスマートフォンでの利用を前提に設計されており、マイナポータルなどの行政サービスなどもスマートフォンでの利用をメインに考えられています。そのため、スマートフォンを持っていないと不便なのは確かです。
スマートフォンを手放すのは現実的ではないでしょう。あくまで、適度な距離感を意識することに重点を置きましょう。
デジタルデトックスを継続するコツ

デジタルデトックスは継続することが大切です。ここでは無理なくデジタルデトックスを習慣化するためのコツをいくつか紹介します。
小さなステップから始める
パソコンにスマートフォン…いきなり全てのデバイスを断つのは難しいかもしれません。そんな時は、小さなステップから始めましょう。
まずは「重要な通知以外をオフにする」とか、「夜寝る前の1時間はスマホを触らない」といった、小さなデジタルデトックスから始めると無理なく取り組めるはずです。
デジタルと関係ない趣味・楽しみを見つける
ITエンジニアはデジタル機器を触っている時間が長い人が多く、仕事に必要な学習もまたデジタル機器によって行われるケースが多くなっています。
そのため、意図的にデジタル機器を使わない趣味や楽しみを作ることも必要です。散歩や読書、料理、スポーツや、友人と食事をしながら会話を楽しむといった、デジタルデバイスを必要としないアクティビティを見つけましょう。
使用ルールを決めて守る
プライベートのLINE、メール、SNSのチェックは、例えば「朝・昼・夕方・夜の4回」などと頻度を決めることで、通知のチェックをきっかけにスマートフォンをダラダラと触ってしまう時間を減らせます。
仕事の連絡に関しては難しい部分があると思われますが、夜間はSlackなどの通知を切るといった方法を取ることで、デジタル機器に振り回されない時間を確保しやすくなるはずです。
デジタルデトックスに挑戦していることを周囲に伝える
家族やパートナー、友人や同僚に、デジタルデトックスを実践していることを伝えるのもおすすめの方法です。サポートしてもらえたり、一緒に取り組む仲間ができたりする可能性があります。また、連絡への返信に以前より時間がかかっても、受け入れてもらいやすくなります。
不慣れなことに一人で取り組むのは大変なことです。デジタルデバイスへの依存性は高く、デトックスするのはなかなか難しいケースも少なくありません。周りの人に知ってもらうことで、成功する確率は高まるでしょう。
最後に
ITエンジニアは、パソコンの前にいる時間が最も長い職業の一つと考えられます。そのため、さらにプライベートでスマートフォンを長時間操作していると、デジタル機器の使い過ぎに起因する体調不良を起こしかねません。それだけに、デジタルデトックスに挑戦する価値は高いでしょう。
デジタルデトックスを行う際は、効果を数値的に把握するために、iPhoneの「スクリーンタイム」、Androidの「デジタルウェルビーイング」を活用することをおすすめします。利用時間が減っていく様子を確かめることで、デジタルデトックスを続けるモチベーションになるはずです。
また、データで可視化するだけでなく、主観的な変化も感じ取れれば、より良いでしょう。デジタルデトックスの効果は人それぞれ異なるため、自分自身の素直な感覚を大切にすることも大切です。