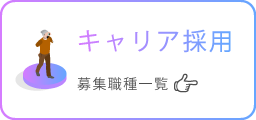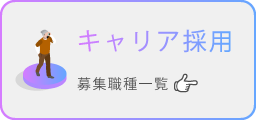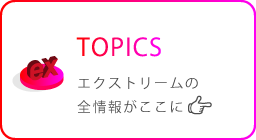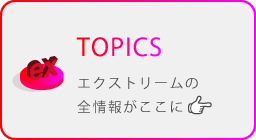クラウドエンジニアとは? 仕事内容や資格、未経験から目指すロードマップなど解説

クラウドサービスの普及が進む中、クラウド技術を支える「クラウドエンジニア」の存在感が増しています。クラウドエンジニアとは具体的にどのような仕事をし、どのようなスキルが求められるのでしょうか?
このコラムでは、クラウドエンジニアの仕事内容や、求められる知識・スキル、未経験からクラウドエンジニアを目指すためのロードマップ、さらには将来性や役立つ資格まで詳しく解説します。
クラウドエンジニアの仕事内容とは?
クラウドエンジニアとは、クラウドサービスを利用してシステムの構築・保守を行うエンジニアのことを指します。近年のクラウドサービスの普及に伴い、需要が伸びている職種です。まずは、クラウドエンジニアの仕事内容をみていきます。
インフラ設計
クラウドエンジニアの主な仕事はインフラ設計です。システムが安定して動作するよう、クラウド環境上のサーバーやネットワークなどのインフラ設計を行います。また、将来的な拡張性を考慮することや、セキュリティ対策を施すことも重要な仕事です。
インフラ設計は裏方的な仕事であり、企業の業務やサービスを滞りなく続けるためには欠かせません。
クラウド環境の構築
クラウドエンジニアは、インフラ設計に加え、クラウド環境そのものの構築も行います。サーバーの仮想化やデータベースの構築、必要なソフトウェアのインストールなどを行い、さらに動作確認や負荷テストも行います。
近年は、業務に必要なシステムをオンプレミス環境からクラウド環境へ移行する企業も多いため、今後さらに活躍の場は広がると考えられます。
保守・運用
構築したクラウド環境の保守・運用もクラウドエンジニアの重要な仕事です。
クラウド環境に不具合が生じると、自社やクライアント企業などに影響を与えます。そのため、不具合が起こったら迅速に原因を究明して復旧させることが求められます。
このように、クラウドエンジニアは、クラウドに関する設計・構築から保守・運用までを包括的に行うエンジニアといえるでしょう。
クラウドエンジニアに求められる知識・スキル
クラウドエンジニアは、クラウドを中心とした技術的知識と、論理的な思考力、コミュニケーション能力などが求められます。ここでは代表的な知識・スキルを紹介します。
1.クラウドに関する知識
クラウドエンジニアにとって、クラウドに関する知識は必須です。
クラウドサービスとして広く利用されている「AWS」や「Microsoft Azure」の知識や、仮想化に関する知識などを習得しておくと役立つでしょう。
また、クラウドに関する技術は日進月歩のため、常に知識のアップデートが必要です。積極的に新しい情報をリサーチし、学ぶ姿勢が求められます。
2.ミドルウェアに関する知識
アプリケーションとOSの中間に存在するソフトウェアである「ミドルウェア」は、サーバーやデータベースとのやりとりなどを担うものです。
クラウド環境の構築やオンプレミスからの移行の際にミドルウェアが必要になるため、クラウドエンジニアにとって、ミドルウェアに関する知識は不可欠といえます。
3.サーバー・ネットワーク・オンプレミスに関する知識
クラウドエンジニアは、サーバーやネットワークに関する知識を求められます。また、オンプレミスとの連携が必要になるケースに備え、オンプレミスに関する知識もあるに越したことはありません。
特にインフラ設計を行う場合は、クラウドの知識だけでは不十分といえるでしょう。それぞれの知識がエキスパートレベルではなくても、広く知識を学んでおくことで、業務が円滑に進みます。
4. AWS・Microsoft Azure・Google Cloudなどの知識
クラウドエンジニアが携わる業務では、AWSやMicrosoft Azure、Google Cloudなどクラウド基盤に関する知識が必要になります。
必要となる知識はそのプロジェクトによって異なるため、すべての知識を身につけておく必要はありません。ただ、これらの知識があれば転職時などに役立つでしょう。
5.ロジカルシンキング(論理的思考力)
ロジカルシンキングとは、物事を論理的に整理し、筋道を立てて推測や理論を考える力のこと。日常生活やビジネスシーンにも役立つスキルです。
クラウドエンジニアには、このロジカルシンキングが特に求められます。なぜなら、インフラ設計やクラウド環境の構築では、論理的に考えて環境を組み立てることが重要となるためです。
トラブルが起きた場合も、原因を論理的に考え、あらゆる可能性を排除せず推論することで、早期に原因の究明ができる可能性が高くなります。
6.コミュニケーション能力
クラウドエンジニアに限りませんが、エンジニアは一人で仕事をするものではなく、プロジェクトごとにチームで業務を行うことが大半です。チームメンバーとの円滑な協力のためには、コミュニケーション能力は欠かせません。
また、立場によってはクライアントからのヒアリングや、他部署との連携も必要になります。協力しながら業務を前に進める姿勢が必要不可欠です。
クラウドエンジニアにとって役立つ資格
クラウドエンジニアは、必須となる資格は特にありません。一方で、自身のスキルの証明として就職や転職時に役立つ資格はあります。ここでは代表的なものを紹介しましょう。
AWS 認定ソリューションアーキテクト
AWS認定ソリューションアーキテクトは、クラウドにおいてトップシェア(約30%)を誇るAWS(Amazon Web Service)が公式に用意している資格です。
AWSにはいくつかの資格があります。AWS認定ソリューションアーキテクトは、AWSのテクノロジーを使用して、安全かつ強固なアプリケーションを構築するスキルに関する資格です。資格には有効期限があり、3年となっています。
Microsoft Azure 認定資格
Microsoft Azureは、クラウド基盤においてAWSに次ぐシェア(約20%)を誇ります。
Microsoftが公式に用意しているAzure認定資格には、三段階の難易度と9つの分野が用意されています。クラウドエンジニアの場合、管理者、開発者、セキュリティエンジニア、データベース管理者などが該当するでしょう。
近年のクラウド技術の進化のスピードを考慮し、有効期限は1年と短くなっています。知識のアップデートを欠かさず、毎年挑戦する必要がある資格です。
Google Cloud 認定資格
Google Cloudは、AWS、Microsoft Azureに次ぐシェア(約10%)があり、徐々にシェアを伸ばしているクラウド基盤です。Google Cloud 認定資格は、Googleが公式に用意する認定資格で11の種類があります。
それぞれ内容や難易度が異なりますが、クラウドの基本概念を問う「Cloud Digital Leader」や、その知識をさらに深掘りする「Associate Cloud Engineer」から挑戦するとよいでしょう。有効期限は通常3年で、プロフェッショナル資格は2年です。
Linux技術者認定試験(LPIC・LinuC)
Linuxはサーバー用としてトップシェアを誇るOSです。クラウド上にサーバーを構築する際にLinuxを使用する機会があるため、Linuxに関する知識があると業務に役立つ可能性が高くなります。
代表的なLinux技術者認定資格として「LPIC(エルピック)」「LinuC(リナック)」があります。LPICはカナダに本拠を置く組織が運営している世界共通の資格で、LinuCは日本市場に最適化された資格です。
国内で仕事をする場合、日本市場に特化したLinuCが適していると考えられます。一方、外資系企業で働く人、海外の開発者と仕事をする機会が多い人は、国際資格であるLPICを受験するとより役立つでしょう。
クラウドエンジニアの将来性・ロードマップ

クラウドの利用は増加傾向にあり、クラウドエンジニアの将来性は明るいと考えられます。ここでは、クラウドエンジニアの将来性と、ロードマップについても解説します。
クラウドエンジニアの将来性
近年は新規プロジェクトがクラウド前提で企画されることも多くなり、オンプレミスからクラウドサービスへの移行も増加傾向にあります。
また、日本政府は政府が取り扱う情報システムを構築する際、第一候補としてクラウドサービスの利用を検討する方針「クラウド・バイ・デフォルト原則」を掲げており、公共事業などでクラウドが利用されるケースも多いものと考えられます。
こうした傾向から、クラウドエンジニアの需要は今後も高まり、将来は明るいと考えられるでしょう。今後、キャリアアップを図りたいエンジニアにとって魅力的な職種といえそうです。
クラウドエンジニアになるためのロードマップ
クラウドエンジニアを目指すには、体系的な学習をすることと、実務経験を積むことが大切です。
未経験の場合、オンラインスクールや専門学校などでネットワーク設計やサーバー管理、セキュリティなどクラウドに関する基礎知識を身につける必要があります。その上で、実際の業務に携わりスキルを身につけていくことが基本となります。
その課程で、AWSやAzureなどの認定資格を取得することも検討しましょう。資格の取得のためにはクラウドについて体系的に学ぶ必要があるため、知識をより深いものにできます。これは経験者でも同様で、自身のスキルを客観的に示せることから転職活動にも有利に働くはずです。
なお、クラウド分野は進化が早いため、クラウドエンジニアになってからも学習の継続が必要です。コミュニティへの参加やオンライン学習の利用などで、スキルセットを維持し続けることが求められます。自己研鑽を続ける努力が必要です。
まとめ
クラウドエンジニアはインフラ設計から構築、保守・運用に至るまで、クラウド全般にわたる幅広いスキルと知識が求められる職種です。また、自己研鑽を怠らず、常に最新の技術を学び続ける姿勢も求められます。
一方で、今後も需要は高まり続けると考えられており、キャリアアップを目指す上でも魅力的な選択肢です。将来性抜群のクラウドエンジニアを目指し、自身のキャリアを大きく飛躍させてみてはいかがでしょうか。