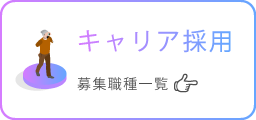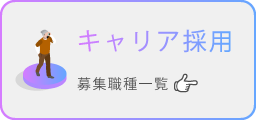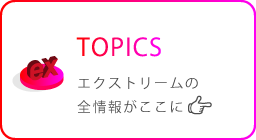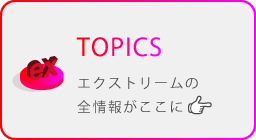両国国技館が熱狂に包まれた5日間
日本開催で“圧倒的ホーム”『ストリートファイター6』世界大会をレポート
1991年にアーケードで登場し、日本中に対戦格闘ゲームブームを巻き起こした『ストリートファイター2』から30年以上。今、日本に再び大きな“格ゲーブーム”が訪れています。
CAPCOMが2023年にリリースしたシリーズ最新作『ストリートファイター6』は、それまで複雑だったコマンド入力を簡略化した「モダン操作」の導入やRPG風のストーリーモードの実装など新規プレイヤーの取り込みに注力。そうした取り組みが奏功し、プロシーンだけではなく配信者などのインフルエンサーとその視聴者層に広く受け入れられ、2024年12月には国内だけで売り上げ100万本を突破しました。
このような背景もあってか、2024年度の公式世界大会の開催地として日本が選ばれ、2025年3月5日から9日の5日間に渡って大相撲の聖地として知られる東京の両国国技館での開催に。

実は『ストリートファイター2』の全国大会もかつて両国国技館で開催されたことがあり、世界大会としては初の日本開催、そして「両国でのストリートファイター公式大会」としては30年ぶりの実施となった大会の模様をレポートでお届けします。
個人、団体共に日本勢が優勝に輝く
今回開催されたのは個人戦の「CAPCOM CUP 11」と、チーム戦の「ストリートファイターリーグ ワールドチャンピオンシップ」の2大会。初日からの4日間は世界各国の予選大会を通過して出場権を獲得した48選手による個人戦が繰り広げられ、最終日は日本、アメリカ、ヨーロッパそれぞれで実施された公式プロリーグ「ストリートファイターリーグ(SFL)」を勝ち抜いた3チーム各4選手が出場しました。
地元開催となる日本勢は「CAPCOM CUP 11」に8選手がエントリーし、予選段階から大きな声援が送られる“ホームアドバンテージ”を得られる会場に。さらに力士がモチーフとなっているキャラクター「エドモンド本田」を使用して勝利する選手も登場し、この「国技館に力士」というシチュエーションは大会期間中でも屈指の盛り上がりを見せるシーンとなりました。

△会場外には今大会専用の“のぼり”も
そんな大会で頂点に輝いたのは、福島県のプロチーム「IBUSHIGIN」に所属する「翔」選手。期間中を通して抜群の安定感を見せ、見事に優勝賞金100万ドルを手にしました。翔選手は2023年にもサウジアラビアで開催された国際大会「Gamers8」を制しており、同タイトルで2度目の世界王者のタイトルを勝ち取りました。
そして翔選手と同じくらいに注目を集めたのは、チリから参加した15歳の新星「Blaz」選手。決して大会前の時点では知名度の高い選手ではありませんでしたが、名だたるプレイヤーを次々と撃破して準優勝の快挙を達成。40代の選手も参加した大会での躍進は、改めてeスポーツが国籍や年齢を問わず競い合うチャンスがある競技であることを示すものであったと言えるのではないでしょうか。
最終日に実施された「SFL ワールドチャンピオンシップ」はチーム戦となったことで、会場はさらに日本を後押しするムードに。決勝戦ではアメリカチーム「Fly Quest」が先に優勝に王手をかけましたが、自然と沸き起こった選手名の大コールに後押しされるように日本チーム「Good 8 Squad」が息を吹き返し逆転。終わってみると個人・チーム戦ともに日本勢の優勝で幕を閉じる結果となりました。

△優勝した「Good 8 Squad」のメンバー
閉会のセレモニーではCAPCOMの代表取締役社長を務める辻本春弘氏が登壇し、来シーズンの施策を発表。CAPCOMのeスポーツがサウジアラビアで開催される大規模大会「Esports World Cup」と3年に渡って連携を強化していくこと、そして来年の世界大会の開催地も再び日本・両国国技館となることが発表されると、会場は大きな歓声に包まれました。
会場の特徴も生かした5日間。光ったMC陣の働きぶり
公式発表によると本大会は5日間での来場者数は延べ1万4千人にのぼり、オンライン配信での総視聴数は複数言語での配信を合計すると1,000万回超という注目度の高いイベントとなりました。
全日程を通じて開演は12時頃でしたが、チケットは事前販売の段階でほぼ完売に。初日からの3日間は平日ということもあって3階席は使用せず、学生割引だけでなく16時以降に入場可能な「ナイト割引」を導入するなど、スケジュールに応じたチケット設定も効果的だったと見られます。

△大型モニターを4面で設置され、3階席からも見やすい会場に
両国国技館ならではの四角く区切られた「升席」もそのまま活用され、グループで観戦を楽しむ来場者の姿も数多く見られました。国技館は過去にも他タイトルでeスポーツ大会の会場となったこともありましたが、やはり他の会場では見られない座席として新鮮さが広く受け入れられているようで、靴を脱いで着席する独特なシステムについても混乱は見られませんでした。
会場内は飲食可能であり、国技館名物の焼き鳥なども軽食も販売されていましたが、食事は基本的に会場外か持ち込みに。近隣にあまり食事を取れる場所がない会場では飲食関連が不便さに繋がってしまうこともありますが、国技館回りはその問題もなく、長丁場の観戦では一時的に会場を離れて食事をとる人も多かったようです。
また、5日間の開催では日本でキャスターとして活躍するアール氏と、世界初のプロゲーマーとしても知られるRyan Hart氏がMCを担当。世界中で注目されているイベントゆえに日本開催であっても英語でのアナウンスは必須となりますが、日本語も堪能なRyan氏が英語アナウンスと通訳の役割を兼任し、海外選手へのインタビューも担当しました。
アール氏もMCで常に会場を盛り立てながら会場内でも音声が流れる日本語配信での実況も兼任する多忙ぶり。通訳を挟みながらの進行も不可能ではなかったと推測されますが、バイリンガルのRyan氏が随時通訳することで非常にテンポの良い進行が実現しており、今大会の成功は両氏の活躍なくしては実現し得なかったと言えるほど、獅子奮迅の働きぶりでした。

△選手の呼び込みや掛け合いによる“繋ぎ”で円滑な進行を実現したRyan氏(写真左)とアール氏(同右)
格闘ゲームでは有力選手を多数抱える強豪国でありながら、なかなか大規模大会の開催地にはならなかった日本ですが、今開催の盛り上がりは相当なものであり、選手からも会場の雰囲気や運営体制について好印象の声があがりました。
何より、時には「おとなしい国民性」とも表現されることもある日本での開催で、今回の「SFL ワールドチャンピオンシップ」の決勝では、ステージを360度取り囲んだ観客席から一斉に日本チームに声援が投げかけられる姿は印象的でした。
タイトルの人気が国内でも飛躍的に高まったことで来場者の熱量も高く、良いムードと日本勢を後押しする“ホーム感”が演出された今大会。既に来年の「CAPCOM CUP 12」と「SFL ワールドチャンピオンシップ」の日本開催も決まっており、今年以上の注目を集めることは間違いないでしょう。
今回は両国国技館という会場、MC陣の尽力。そして日本人プレイヤーが世界的に活躍し人気が高まっているジャンルという複数の条件が大きな魅力となっていたのは間違いありませんが、さまざまな国籍の参加者が集まる会場内でも、そして配信上でも大きなトラブルや遅延なく5日間という長丁場の大会を成功させた運営能力は非常に素晴らしいものでした。
スムーズな進行とコンパクトかつガイドの充実した会場設計、選手の環境を優先しながらも来場者を退屈させない施策など、奇抜さはなくとも重要な要素が詰まった大会となっており、今後どのようなジャンルの大会であっても参考にできる事例になったのではないでしょうか。
2025年1月には北海道で『Apex Legends』の世界大会が実施されており、今後さらに「eスポーツの世界大会を開きやすい国」として、日本とそのeスポーツコミュニティが注目されていく可能性も期待されます。